2019.08.20
「これはルールだから」と融通のきかない人事担当者は嫌われるもと。
とはいえ、人によってルールを変えていてはルールとして機能しません。
柔軟に対応することが大切ですが、
ではどのようにバランスをとればよいのでしょうか?
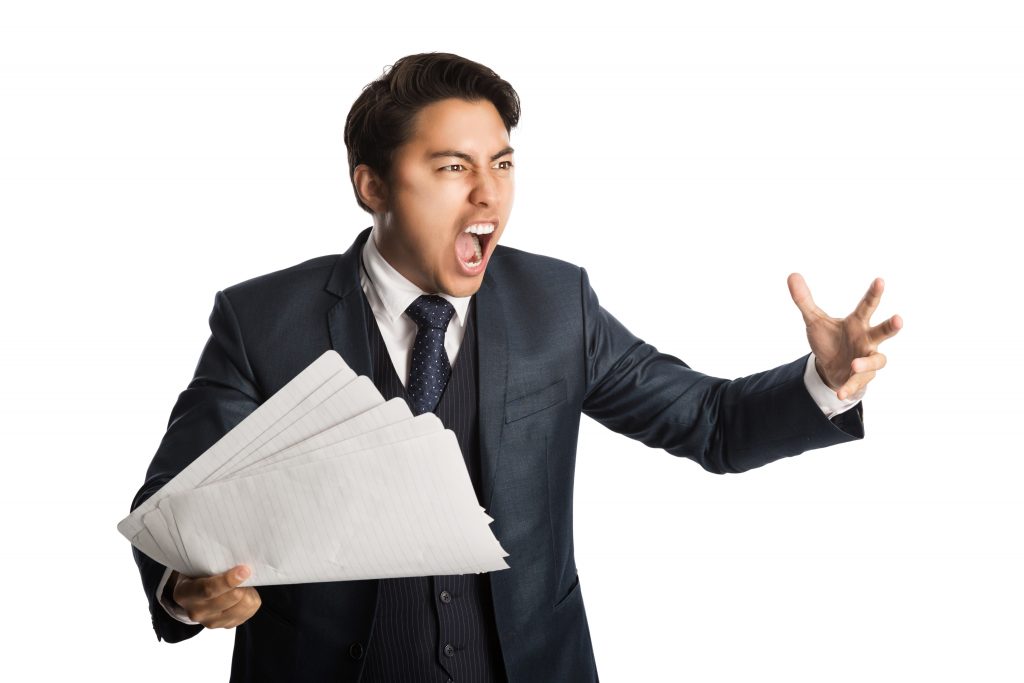
組織長、あるいは社員から相談事を受けた時に「会社のルールなので、できません」と人事担当者に取りつく島もなく断られる。こういった場面は、多くの企業に見受けられるものです。しかし、人事には意外と「遊び」や「バッファ」といったバランス感覚も必要とされます。その理由をお伝えしましょう。
お役所仕事のように「あれもダメ、これもダメ。ルールですから!」と杓子定規に切り捨ててしまう人事担当者。このコラムをお読みの方も、一度は遭遇されたことがあるかもしれません。
そういった態度は、人事の業務における失敗のもとです。これから人事の仕事に携わる、もしくは現在携わっている人は、自分の特性について一度考えてみてください。もし、自分のコンピテンシー、あるいはパーソナリティとして、こうした「遊び」「バッファ」などが欠けている、と思うのであれば、余計に意識したほうがよいでしょう。
では、なぜ人事担当者にはそのような柔軟性が必要なのでしょうか。
まず、あくまで人事というのは会社の経営上の目的を、あらゆる組織、人を動かしながら実現させるための部門です。面接をしたり、給与計算をしたりなどの業務はあくまで目的達成のための部分的な作業でしかありません。
人事上の様々なルールは、経営上の目的を達成するために定められています。しかし、会社には部署ごとに分かれており、新卒も中途も、様々な背景の人が働いています。そのため、全社で共通するルールを決めたとしても、部署によって運用が難しい場合があるのです。その場合、ルールの柔軟性をあらかじめ確認した上で運用していく必要が出てきます。
「人や部署によってルールを変えていては、不公平が生まれるのではないか」。そう考える人事担当者の方もいるかもしれません。
確かに、社員同士で不公平になることも出てくる可能性があります。しかし、その不公平さも飲み込んで実務を行うことが経営上の目的を達成するために必要なのであれば、柔軟に運用することも考えなければならないでしょう。

とはいえ、柔軟に運用しすぎては、ルール自体が形骸化してしまい、組織運営を混乱させかねません。「ここだけは譲れない、超えてはいけない一線」をどこに引くか、という点は判断基準を持つ必要があります。
この超えてはいけない一線は「門」と言い換えることもできます。「人事は門番」という言い方を、この業界ではよく使います。あなたが最後の門を守っているならば、「自分の守っている門は一体どういう門なのか」を具体的に理解し、自分の中に落とし込んでおく必要がありますね。
落とし込みを経て、自分なりの基準はもちろん持っておくべきですが、運用を始める前には、あらかじめ経営陣や人事の組織長とすり合わせをし、整合性が取れているか確認をしておくとよいでしょう。自身で案を作った上で上司の承認をもらい、現場に運用に適用する、という順序であれば、混乱を招くリスクは少なくなります。
人事は、会社側の人間と思われることもありますが、会社と社員、50:50でバランスを取る必要がある立場です。経営の目的を達成する必要がある一方で、「社員=お客様である」という視点も必要になります。自分のバランス感覚がどちらか一方に偏っていないか、チェックする良い機会にもなるかもしれません。
繰り返しになりますが、人事にはあらゆる制度に目的があります。ルールで縛ることそのものが目的ではありません。多少ルールを曲げてでも、目的達成を上位に置くべきです。ルールを曲げた際に生じる不公平さがどの程度のものなのか、影響と対処策は考えた上で実施するように心がけてください。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊
成果主義、職務主義、年俸制、人事部廃止… 90年代から変わらぬ「人事」の構造、変わらぬ平均給与額が、日本を世界トップクラスの「社員が会社を信頼しない国」へと導いたのです。
なぜ変革が進まないのか、その背後に潜む「考え方」の欠如とは何でしょうか?

中学時代に習ったこと、覚えてますか?
多くの人にとっては、すべての勉強の基礎になっている大事な「当たり前」のことですが、思い出せと言われても思い出せる方は少ないでしょう。
この「この一冊ですべてわかる 人事制度の基本」には、人事の当たり前が詰まっています。

ー「なぜ、あの人が?」
なぜ多くの企業で「評価基準」が曖昧になっているのでしょうか。
どうすれば給与が上がるのでしょうか。
11,000人超の人事担当者から絶大な支持を得るコンサルタントが、今まで9割の会社が明かさなかった「絶対的な指標」を初公開!

テレワーク時代には「ジョブ型」に留まらず、「超ジョブ型人事」が不可欠。
その一番の理由は、テレワークをはじめとするこれからの働き方には「監視しない事が重要であるから」です。

人事の“必須科目”を押さえる
プロの人事力
次のステージに向けて成長するためのキホン
人事担当者に必要な知識・学び方、仕事に対する心構え、業務との向き合い方、さらには人事マネージャー、人事部長へとキャリアアップするために必要な能力・スキルを一挙公開

総合人事コンサルティングのフォー・ノーツ株式会社は、代表取締役社長・西尾太の著書『この1冊ですべてわかる 人事制度の基本』出版記念特別セミナー【聞いた後でジワジワくる‼西尾太の「地味な」人事の話】を2022年11月17日、TKP東京駅日本橋カンファレンスセンターにて開催いたしました。本記事は、このセミナーの内容を再構成・加筆してお届けしています。今回のテーマは「制度づくり」。職位制度・評価制度・給与制度の大事なポイントを簡単に説明します。

リストラが増えています。コロナ禍の影響だけでなく、実はそれ以前から70歳までの雇用延長努力義務などを見据えて「黒字リストラ」と言われる施策をとる企業が増えていました。終身雇用や年功序列も終わりを迎えようとしています。40歳を過ぎたら希望退職を勧められてしまうかもしれません。今、求められているのは、いざという時に他にも行ける力です。今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、「どこでも通用する力」を育む、評価基準のつくり方を解説します。

フォー・ノーツ株式会社が運営する【公式】YouTubeチャンネル。 今回は、【テレワークの評価目標はこうやって決めるコツ】について現場を知り尽くした人事のプロ・西尾 太が解説いたします。

フォー・ノーツ株式会社が運営する【公式】YouTubeチャンネル。 今回は、【経営者と労働者それぞれの観点から考えるベストな働き方】について現場を知り尽くした人事のプロ・西尾 太が解説いたします。

創業したてのベンチャーから成長後期、大企業クラスの規模に至るまで、
会社には様々な変化があります。そしてそれは、人事部も同じ。
今回は各ステージごとの人事部の立ち位置の違いと、
人事が陥りがちなことをお伝えします。

最近の検証で、職場に「ホーム感」を抱いている人材は、
業務でのパフォーマンスも高い傾向が分かってきました。
・「ホーム感」とは何なのか
・なぜ職場に「ホーム感」を抱いている社員はパフォーマンスが高いのか
この記事では以上の2点を解説していきます。

採用活動に欠かせない「求める人物像」。なんとなくでごまかしていませんか?
今回は「自社の立ち位置」と「会社の価値観」「成果につながる要素」をポイントに、
求める人物像の定め方を紹介していきます。

360度評価とは、「上司が部下を評価する」という従来の評価手法とは異なり、部下や同僚なども人事評価を行う評価方式です。この手法を導入する場合、どのような点に注意したらいいのでしょうか? そこで今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、リアルな事例から360度評価のメリット・デメリットについてお伝えします。