2019.06.28
労務分野の法律や制度に関する「お勉強」が
人事担当者の第一歩だと勘違いしてしまっている方は少なくありません。
しかし実は、人事担当者には専門的な知識など必要ないのです。
この記事では人事担当者に求められる知識を解説していきます。
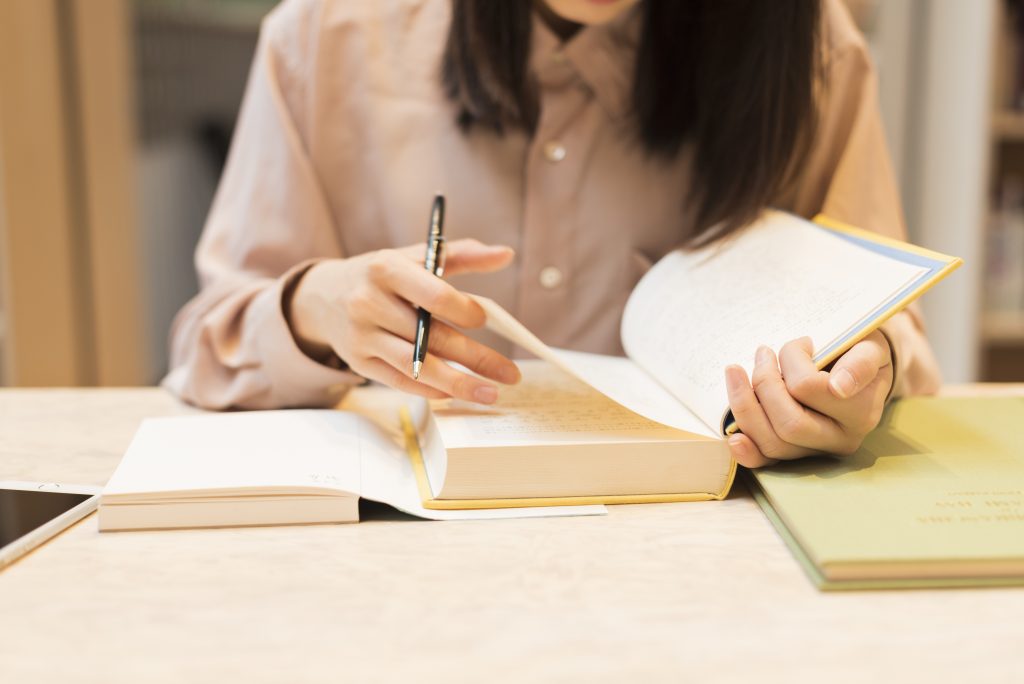
人事の仕事は実際にやってみないとイメージしづらい部分も多く、初めて人事を担当することになった方にはわからないことだらけだと思います。そこで今回は、多くの新任人事担当者が思う「人事担当者にはどのような知識が必要なの?」という疑問にお答えしていこうと思います。
「人事に関する知識」と聞いてまず思い浮かべるのは、労務など人事領域に関連する法律知識ではないでしょうか?法律や制度をマスターすることが人事担当者としての第一歩だと思っている方も少なくないように感じます。
しかし、専門的な法律知識は実はそこまで重要ではありません。なぜなら、法律知識はその分野の専門家、例えば労務関係であれば社労士に聞けば解決することだからです。法律の丸暗記や過去の判例の収集といった「お勉強」は必要ないのです。
ただし、高度に専門的である必要はありませんが、最低限の知識は必要です。何も知らないでいい、というわけではありませんのでご注意ください。
知識の深さとしては、専門家と会話ができるレベルを目安にしてください。何かを専門家に相談しても、専門家の言っていることが理解できなければ、それは情報を表面上だけでやり取りしている伝言ゲームにすぎません。会社と専門家との間に人事が立つ意味は、情報をかみ砕き、会社の考えを適切に専門家に伝え、専門家の言葉を適切に会社にフィードバックすること。それを実現するために、最低限の法律に関する知識が必要になるのです。

それと並行して、専門的な知識にアクセスする手段を確保しておくことも人事には求められます。例えば社内から何らかの質問が上がってきたとき、「どの本を調べればわかるか」「誰に聞けばわかるか」が明確になっていれば、すぐに対応することができます。
しかしその問題に関する知識がなければ、手探り状態で進むしかありません。仮に最後には解決できたとしても、かなりの手間と時間が必要になるでしょう。聞くべき専門家を間違えると余計な費用が発生してしまったり、時には信用を失ったりもします。効率よく問題を処理していくためにも、専門的な知識へのアクセス手段は常に意識しておくようにしましょう。
ここで注意しておいてもらいたいことは、専門的な知識にアクセスした結果(「法律ではどの条項で規定されているか」「どの判例を典拠にしているか」といった専門知識)を覚える必要はないということ。繰り返しになりますが、丸暗記はその分野の専門家の仕事です。以前聞いたことを忘れてしまっても問題はありません。向こうもそれが仕事のひとつと思い、遠慮せずに聞いてください。
人事は人事施策の専門家であり、法律知識の専門家ではない。この意識を忘れないようにしてください。
反対にぜひ学んでおいてほしいことは「人事とは一体何か」「どのようなことが求められているのか」といった、人事に関する基礎知識です。この部分はいわば人事の専門分野ですから、深く踏み込んで取り組む必要があります。書籍でも構いませんし、セミナーなども開催されています。積極的に活用してください。
他には、人事関連のニュースも知っておいて損はありません。例えば働き方改革に関する法改正などは、詳しく知っておく必要はないものの、「どのようなことが行われるのか」「目的は何か」「人事としてどんな対応が必要になるのか」は理解しておくべきでしょう。社内の誰かに尋ねられた時、簡単に説明できる状態がベストです。
また、他の企業は実際にどのような人事施策を行い、どういった効果を上げているのかの情報収集も怠らないようにしてください。他社の動向を参考にしながら、適宜自社の人事制度をアップデートできる体制を作っておくことが大切です。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊
成果主義、職務主義、年俸制、人事部廃止… 90年代から変わらぬ「人事」の構造、変わらぬ平均給与額が、日本を世界トップクラスの「社員が会社を信頼しない国」へと導いたのです。
なぜ変革が進まないのか、その背後に潜む「考え方」の欠如とは何でしょうか?

中学時代に習ったこと、覚えてますか?
多くの人にとっては、すべての勉強の基礎になっている大事な「当たり前」のことですが、思い出せと言われても思い出せる方は少ないでしょう。
この「この一冊ですべてわかる 人事制度の基本」には、人事の当たり前が詰まっています。

ー「なぜ、あの人が?」
なぜ多くの企業で「評価基準」が曖昧になっているのでしょうか。
どうすれば給与が上がるのでしょうか。
11,000人超の人事担当者から絶大な支持を得るコンサルタントが、今まで9割の会社が明かさなかった「絶対的な指標」を初公開!

テレワーク時代には「ジョブ型」に留まらず、「超ジョブ型人事」が不可欠。
その一番の理由は、テレワークをはじめとするこれからの働き方には「監視しない事が重要であるから」です。

人事の“必須科目”を押さえる
プロの人事力
次のステージに向けて成長するためのキホン
人事担当者に必要な知識・学び方、仕事に対する心構え、業務との向き合い方、さらには人事マネージャー、人事部長へとキャリアアップするために必要な能力・スキルを一挙公開

評価制度の導入は会社にとっての変化。
中には良く思わない人もいるかもしれません。
しかし、だからといって引き下がると制度の導入が進められないばかりか、
人事が“なめられる”原因になってしまいます。

新型コロナウイルスの影響によって消費が落ち込み、飲食店やショッピングモールなどの営業自粛も相まって、業績が低迷している企業が増えてきました。 こうした緊急事態、かつ長期戦が見込まれる時こそ、企業は数年後の展望を見据えた事業戦略を立てることが大事です。 こうして立てられた事業戦略をもとに今後の人事戦略を考えていきましょう。

新しく人を雇う新規採用は、多くの企業が困っているところです。
「せっかく雇ったのにすぐやめてしまう」「求める社員が来てくれない」。
これらの原因は、意識のミスマッチであることがほとんど。
人事ポリシーを利用して、応募者と事前に意識をすり合わせておきましょう。

今再び注目を集める「ジョブ型雇用」や「成果主義」。 決して新しい考え方ではありませんが、これからの働き方を考える中では重要な要素です。これらの導入には、ジョブディスクリプション(職務記述書)が必要ですが、策定や運用には多くの困難が存在します。 今回は代表西尾から、これからの時代の働き方や評価についてお伝えしていきます。

若手人事が必ず悩む、現場との距離感の問題。
実際にどのように現場と付き合っていけばよいのか、
人事での経験を元にお話しいたします。
「あ、これは危ないかも」と気づくヒントにしていただけますと幸いです。

コロナウイルスの影響で、賞与のカットや社員の解雇が話題となっています。 「一時帰休」というワードを目にすることも多くなったのではないでしょうか。 当然しないに越したことはない「解雇」ですが、この情勢下、それでも考えなければならない方も多いはず。今回は企業の業績低迷時に決断しなければならない、賞与カットや昇給停止、そして解雇について解説します。

パワハラの防止措置は、大企業では2020年6月1日から雇用者側の義務となりました。中小企業でも2022年4月1日より適用されます。そこで今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、ハラスメント研修の目的やその必要性について解説します。

新卒の3割は3年で辞めてしまう。これは昔から人事担当者の常識のようになっていましたが、近年は半年未満で辞めてしまう人も増えているようです。なぜ新卒はすぐに離職してしまうのでしょうか。実は「若い人が辞めていく企業」には共通する特徴があります。あなたの会社は大丈夫ですか?