2018.10.18
人事評価制度は、社員の育成のために必要不可欠です。
しかし間違った評価基準を設けてしまうと、
社員の成長どころか企業の業績の低下にもつながってしまいます。
ではどのような点に注意すればよいのでしょうか?
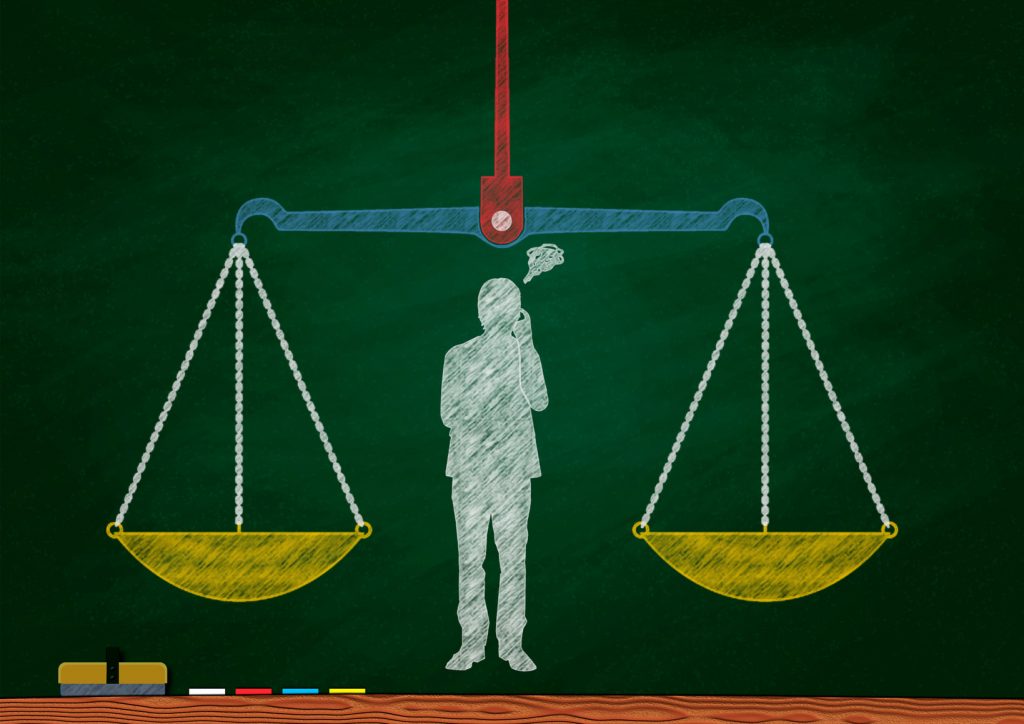
人事評価制度は、社員の育成のために必要不可欠です。人事評価制度を作成しようと考えた際に問題となるのが、「絶対評価」か「相対評価」か。果たして、どちらの方が人事評価に向いているのでしょうか?
結論から言うと、人事評価に向いているのは「絶対評価」です。絶対評価とは、評価基準に照らし合わせて一人ひとりを評価する方法です。社員の役職など等級によって異なる評価基準はありますが、決められた基準に合わせて個々の能力や実績を評価するため非常に明確です。
しかし、日本の多くの企業では、「人」を評価する際には、どうしても相対評価になりやすいと言われています。相対評価とは、同じグループ内の他のメンバーと比較して順位をつけをする評価方法です。もちろん、相対評価が必ずしも悪影響を及ぼすとは限りませんが、評価制度においては『明確な評価基準』が必要になります。というのも、評価の際には「公平さ」を重んじ、社員本人も他の写真も納得する評価を与えなければなりません。相対評価ではこの「公平さ」が欠けがちになってしまいます。
逆に言えば、評価基準が明確になっていない企業は相対評価になりやすいと言えます。たとえば成果を挙げていない人間に対しての「〇〇は頑張っている」という評価。確かにその社員は頑張っているのでしょう。しかし、果たして他の社員は頑張っていないのでしょうか?頑張っているのはみんな同じなのではないでしょうか?成果を挙げていないのに「頑張っている」と評価してしまうのは、おそらく評価している人の私情が入っていると思われますし、他の社員もそう考えるでしょう。それは果たして、公平な評価と言えるでしょうか。
繰り返しになりますが、相対評価は絶対悪というわけではありません。しかし公平さを持つという観点に立った時にはリスクが高いため、絶対評価の基準を設けた方がいいのです。
さて、私情が入った評価のお話をしましたが、おそらく多くの方が「評価に私情を入れるのは悪いことだ」という自覚があると思います。では、なぜよくないのか、考えたことがありますか?
多くの方は「昇進や昇給が上司に気に入られるかどうかで決まるから」と答えると思います。確かに自分の能力が正当に評価されないのは非常に残念な事態です。でも「評価には上司の私情が入る」と知っているのであれば、その前提を踏まえた働き方をすればいいだけのこと。それでもどことなく不健康で、悪いことに感じるのはなぜでしょうか?
その理由は、「社員が成長しなくなる」「社員の成長スピードが遅くなる」という点にあります。「上司に好かれれば、評価される」このような考えは成長を抑制するだけでなく、スキルのない人が昇進してしまい会社全体の業績が下がることにもつながるのです。もちろんそのような人間が評価されることによって、社員のモチベーションも下がります。
つまり、会社の未来を考えるのであれば、人事評価を相対評価で行うことはデメリットしかありません。
絶対評価は公平な評価です。一番わかりやすい例をあげると営業の人にとっての月の契約件数がありますが、勤務態度の面では「1年間の事故件数」なども評価基準になりえます。「1年間無事故無違反」というのは立派な評価になりえます。
上述のように「評価基準」は明確に設定し、設定するだけでなく、かならずあらかじめ周知しておくべきです。そうすれば社員はその評価基準項目に沿って仕事をする、つまり明確な目標が定まります。目標を達成するためにはどのように行動すればよいのかを自ずと考え、勉強を怠らなくなります。効率的に成長してもらうことができるのです。
もちろん、評価基準は会社の「人事ポリシー」に則ったものを作らなければなりません。人事ポリシーと評価基準がブレていたら、社員はどちらを参考にしていいのか迷ってしまいます。
評価の曖昧さは時に現場を混乱させ、業務すら妨害してしまいます。会社にとってそれはあってはならないこと。多少のコストや手間をかけてでも、絶対評価の評価基準を設けることが大切です。
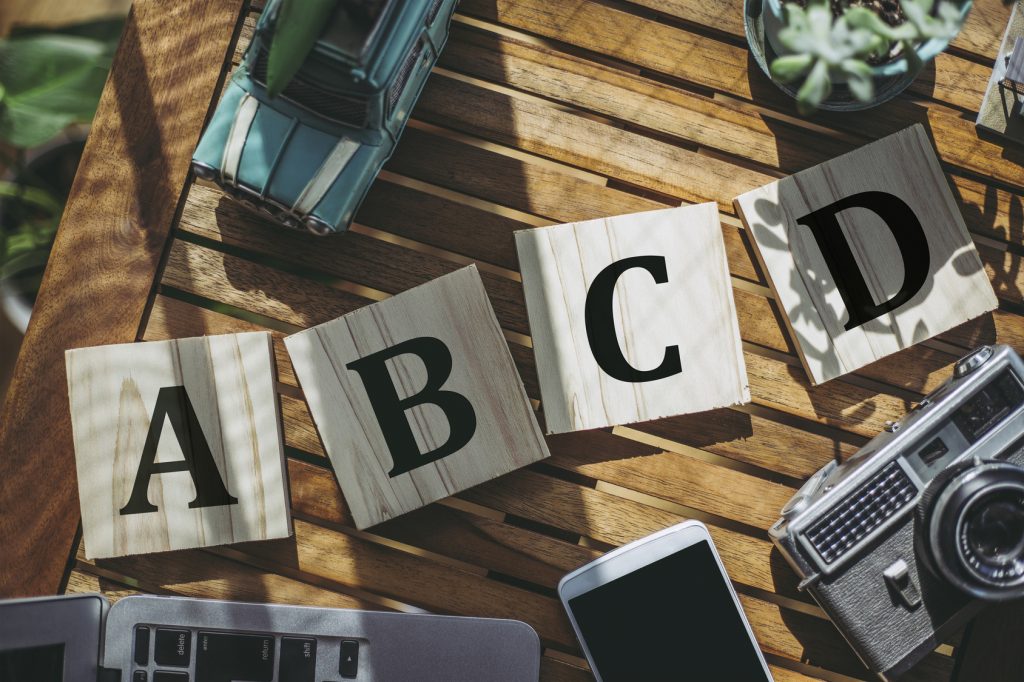
評価の方法として、一般的に「評点制」と「評語制」があります。先程、絶対評価はノルマのような数字だけではないとご説明しましたが、人の評価を段階で表すときは、「評点制」ではなく「評語制」をお勧めします。
評語制とは、文字のとおり評価を言葉で表す制度です。評点制の場合、たとえば5段階であれば、1~5の数値で表されます。それを「SS/S/A/B/C」などの表し方をするのが評語制です。大学における評価などは、評語制を用いているところが多いですね。逆に高校の通知表では、評点制を用いている場合が多いと思われます。
私たちはさらに、評語制の文字を記号とするのではなく、さらに意味を持たせた方がよいと考えています。「SS/S/A/B/C」という段階を設けるのであれば、SS「超すげえ!」S「すげえ!」A「ありがとう」B「挽回しよう」C「かなり挽回しよう」といった具合です。
ここで重要なのはネガティブな言葉に変えないことです。特にBやC評価の社員に対し、「もっと頑張れよ」や「君は仕事ができない」などとネガティブな言葉を使うことは厳禁です。モチベーションが削がれるうえ、精神的にもあまり良い影響がありません。逆にポジティブな言葉をかければ、信頼を得ることができるだけでなく、「頑張って自分の評価をあげよう」という気持ちになりやすいと言われています。社員自ら、目標を立てて成長するようになるのです。
評点制には、評価対象が人間であるにも関わらず、機械的な処理をされているように感じる人もいます。絶対評価は、相対評価に比べると事務的な印象を受けるかもしれません。その分、このように「言葉で伝える」ということを意識すれば、コミュニケーションが生まれ、意識のズレも発生しにくくなります。積極的に言葉で伝えていきましょう。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊
成果主義、職務主義、年俸制、人事部廃止… 90年代から変わらぬ「人事」の構造、変わらぬ平均給与額が、日本を世界トップクラスの「社員が会社を信頼しない国」へと導いたのです。
なぜ変革が進まないのか、その背後に潜む「考え方」の欠如とは何でしょうか?

中学時代に習ったこと、覚えてますか?
多くの人にとっては、すべての勉強の基礎になっている大事な「当たり前」のことですが、思い出せと言われても思い出せる方は少ないでしょう。
この「この一冊ですべてわかる 人事制度の基本」には、人事の当たり前が詰まっています。

ー「なぜ、あの人が?」
なぜ多くの企業で「評価基準」が曖昧になっているのでしょうか。
どうすれば給与が上がるのでしょうか。
11,000人超の人事担当者から絶大な支持を得るコンサルタントが、今まで9割の会社が明かさなかった「絶対的な指標」を初公開!

テレワーク時代には「ジョブ型」に留まらず、「超ジョブ型人事」が不可欠。
その一番の理由は、テレワークをはじめとするこれからの働き方には「監視しない事が重要であるから」です。

人事の“必須科目”を押さえる
プロの人事力
次のステージに向けて成長するためのキホン
人事担当者に必要な知識・学び方、仕事に対する心構え、業務との向き合い方、さらには人事マネージャー、人事部長へとキャリアアップするために必要な能力・スキルを一挙公開

現状維持を好む安定志向の若者が増えてきていると言われています。
その考え方は本当に「安定」につながっているのでしょうか?
そして、現状維持を好む若手の成長を促したい場合、
人事担当者・経営者がすべきこととはなんでしょうか?

明確な人事評価制度を持っている企業はほんの一握りだと言われています。
しかし社員の成長、ひいては会社の成長のためには、
評価基準を作り、人事評価制度を導入することが必要不可欠です。
ではそのメリットはどこにあるのでしょうか?

不正やパワハラなど、内部告発によって明るみに出る企業の不祥事。内部告発はとても勇気のいる行為ですが、人事に影響するのか、どんなデメリットがあるのか、気になる人も多いでしょう。そこで今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、内部告発に対して会社や人事担当者がすべきことを解説します。

人事は、人員計画・配置・採用・給与・厚生・育成・評価といった分野と、それぞれに戦略、企画、運用、オペレーションという機能があり、幅広い分野の領域に関わる職種です。一領域の人事担当者からマネジャー、人事責任者になるには、何をどのように学べばいいのでしょうか?本記事では、担当者レベルから人事責任者を目指すために重要なポイントを「人事の学校」主宰・西尾太が解説します。

会社にとって社長は意思決定者であり、常に先頭を走り続ける存在です。
それでも、いつでも正しい判断ができるわけではありません。
社長の指示や行動が会社の人事ポリシーに沿わない場合、
自信をもって「待った」をかけられる人事担当者になってください。

フォー・ノーツ株式会社が運営する【公式】YouTubeチャンネル。 今回は、【経営者と労働者それぞれの観点から考えるベストな働き方】について現場を知り尽くした人事のプロ・西尾 太が解説いたします。

最近の検証で、職場に「ホーム感」を抱いている人材は、
業務でのパフォーマンスも高い傾向が分かってきました。
・「ホーム感」とは何なのか
・なぜ職場に「ホーム感」を抱いている社員はパフォーマンスが高いのか
この記事では以上の2点を解説していきます。

総合人事コンサルティングのフォー・ノーツ株式会社は、代表取締役社長・西尾太の著書『この1冊ですべてわかる 人事制度の基本』出版記念特別セミナー【聞いた後でジワジワくる‼西尾太の「地味な」人事の話】を2022年11月17日、TKP東京駅日本橋カンファレンスセンターにて開催いたしました。本記事は、このセミナーの内容を再構成・加筆してお届けしています。今回のテーマは、「何に対してお金を払うのか?」。人事制度設計の根本的な考えを整理しましょう。