2018.09.26
「自分の将来が見えない」と感じる会社に所属し続ける人はなかなかいません。
会社が評価制度を作り、求めるものや進むべき道を照らしてあげれば、
社員はおのずと努力し成長するようになります。

会社は常に悩みをいくつも抱えています。その中の頭の痛い悩みの一つが「人」に関する悩みです。「人の悩み」と一言でいっても、離職や社員の育成、個々の業績など、悩みは様々。そんな悩みを抱えている会社には共通して、『「評価制度」が策定されていない』という特徴があることをご存知でしょうか。
実は、評価制度を策定するだけでこれらの悩みが一気に解消することがあります。評価制度を策定しているが、人の問題をまだ抱えているという会社についても、評価制度を見直すだけで変わることもあります。評価制度が機能している状態にするだけで「人」の悩みは解消するのです。
評価制度の話に入る前に、そもそも、なぜ離職や社員の育成に関する悩みが発生してしまうのでしょうか。離職の原因は様々ですが、中でも新卒など新入社員に多いのが「先が見えない」と言う不安です。この不安というのは、どうしても個人差がありますが、「先」という言葉がポイントです。
「先」とは、将来のあるべき自分の姿のことをさします。「このまま仕事をしていても…」という不安が大きくなるにつれて、「転職」と言葉が頭にちらつき始めるのです。逆に言えば、将来のあるべき自分の姿をイメージさせることで、将来への不安はかなり軽減することができます。将来のあるべき自分の姿、つまり「キャリアビジョン」を社員に共有する際に有効な手段が、評価制度なのです。
なぜ評価制度があれば、キャリアビジョンをイメージすることができるようになるのか。それは、会社にとって自分がどのように評価され、何を求められ、今、何が必要なのかがはっきりするからです。
この「何が必要なのか」がわかることで、会社の求める自分と同じベクトルで目標を立てることが出来ます。もちろん、会社が求めていることができるのですから評価も上がります。会社に必要とされている自分を認識することでモチベーションも向上します。
単純なようですが、「不安」が「社員の成長」を抑制しているのです。不安がなくなれば、社員が自ずからあるべき将来の自分に必要な勉強をはじめることも少なくありません。
これは社員の成長についても同じことがいえます。「社員がなかなか成長しない」という悩みを持っている管理職の方も多いと思いますが、その理由の多くが企業が成長のベクトルを社員に示しせていないことにあります。簡単に言うと、社員に何も持たせずに、広い荒野に放ってしまっている状態なのです。たとえば会社が「右に行ってほしい」と思っても、社員が進んでほしい方向を知らずに左に行ってしまえば、会社の成長にはつながりません。
しかし、社員は左の方向に成長しているのです。つまり、「自分としては成長しているつもりなのに会社が全く評価してくれない」という状態に陥ってしまいます。
社員と会社のベクトルが真逆の方向を向いてはお互いにとって不幸です。会社の向いてほしい方向を社員に示したり、右に道をつくれば、自ずと社員は右に行くでしょう。つまり、評価制度は会社の指し示したい道を社員に示すためにあるのです。
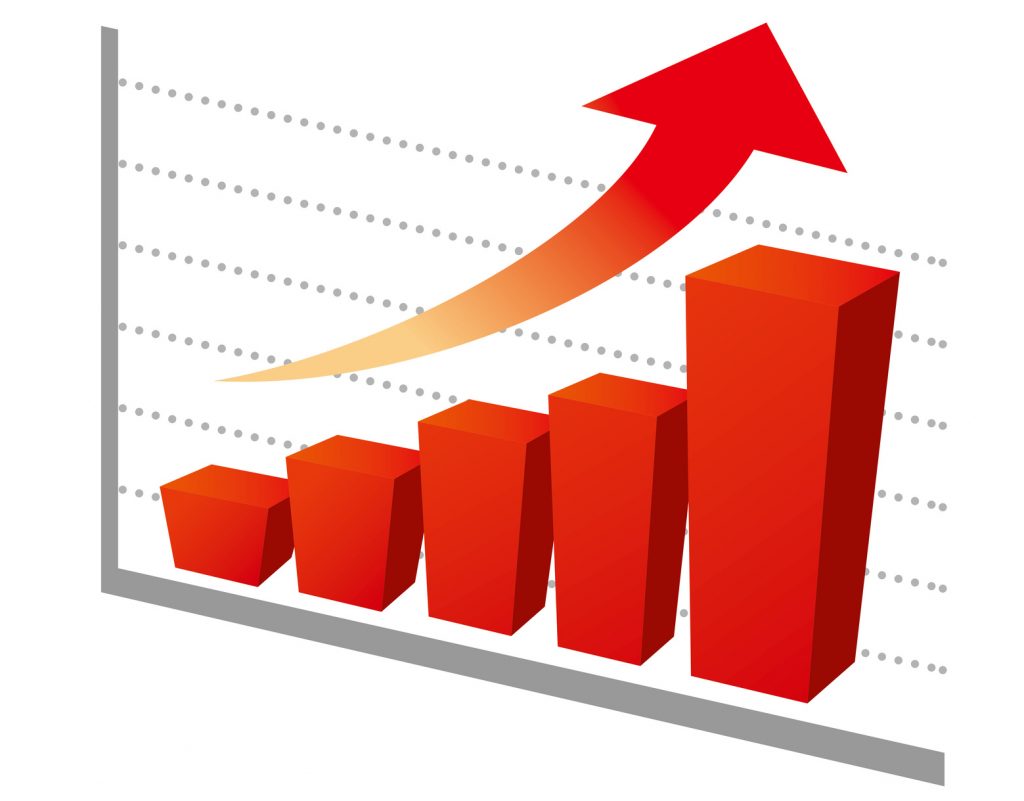
先述の通り、評価制度には離職を防止し、社員の育成を効率的に行う効果があります。社員の個々の成長により、ポテンシャルが上がると、業績はみるみる上がります。たとえば業績不振だった社員がやるべきことを理解した結果、安定した業績を上げられるようになったり、採用にも効果を発揮して優秀な社員の人数が増えたりなど、会社全体のポテンシャルも格段に上がるのです。
会社全体の業績が上がると社内の雰囲気もポジティブな雰囲気になりますよね。この、ポジティブな雰囲気はより一層仕事効率を上げ、更なる業績アップにつながります。
さて、評価制度がいかに重要かは理解していただけたかと思いますが、そもそもこんなにメリットがある評価制度を策定していない企業が多いのはなぜでしょうか。これは簡単に言うと、策定の仕方が分からないのです。「評価制度が必要だから今すぐ策定しよう」と言われて、急につくれるものでしょうか。もちろんかなり労力がかかりますし、正直に言いますと、仮につくれたとしても十分に効果を発揮できる制度をつくることは到底無理です。
そう、今まで意識していなかった人がいきなりつくれるようなものではありません。評価制度の策定は人事の仕事ですが、だからと言って突然「つくれ」と言われても戸惑ってしまいますよね。かといって、人事に長けた人物を新たに雇おうとすると、その会社のことをよく知らないまま策定をすることになるので、慎重に進めないと会社の方針とは違う評価制度をつくってしまうということにもなりかねません。では、どうしたらいいのでしょうか。
その答えは、「人事を雇う」のではなく「人事を教わる」ということにあります。今まで人事をしていた人もしていなかった人も、会社に長く勤めているのであれば雰囲気や方針はある程度わかっているでしょう。その理解は、会社に合った評価制度の策定に必須です。
人事を教わる、とは言いましたが、受動的に構えているだけでは教えてくれる人も見つかりません。たとえば人事に関する本をたくさん読んだり、セミナーや勉強会に参加したり、いろいろ行動してみましょう。とくにセミナーや勉強会は、同じような悩みを持つ人が集まっているので精神的負担もかなり軽減されると思います。まずは一歩、踏み出してみてください。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊
成果主義、職務主義、年俸制、人事部廃止… 90年代から変わらぬ「人事」の構造、変わらぬ平均給与額が、日本を世界トップクラスの「社員が会社を信頼しない国」へと導いたのです。
なぜ変革が進まないのか、その背後に潜む「考え方」の欠如とは何でしょうか?

中学時代に習ったこと、覚えてますか?
多くの人にとっては、すべての勉強の基礎になっている大事な「当たり前」のことですが、思い出せと言われても思い出せる方は少ないでしょう。
この「この一冊ですべてわかる 人事制度の基本」には、人事の当たり前が詰まっています。

ー「なぜ、あの人が?」
なぜ多くの企業で「評価基準」が曖昧になっているのでしょうか。
どうすれば給与が上がるのでしょうか。
11,000人超の人事担当者から絶大な支持を得るコンサルタントが、今まで9割の会社が明かさなかった「絶対的な指標」を初公開!

テレワーク時代には「ジョブ型」に留まらず、「超ジョブ型人事」が不可欠。
その一番の理由は、テレワークをはじめとするこれからの働き方には「監視しない事が重要であるから」です。

人事の“必須科目”を押さえる
プロの人事力
次のステージに向けて成長するためのキホン
人事担当者に必要な知識・学び方、仕事に対する心構え、業務との向き合い方、さらには人事マネージャー、人事部長へとキャリアアップするために必要な能力・スキルを一挙公開

人手不足の解消は、多くの人事にとって切実な課題となっています。人材を確保する手段は、正社員だけではありません。それは「正社員」でなければならないのか。人事担当者は、慎重に検討しなくてなりません。正社員雇用の際には、「留意すべきポイント」があります。

企業が新たな人材を獲得する方法には大きく分けて、新卒採用と中途採用の二つがあります。各々の特徴について、ご自身のイメージを持たれているのではないでしょうか。ですが今一度、これからの時代に合った人材採用の考え方を考えていきましょう。 また、コロナ禍における新卒採用の捉え方についてお話しいたします。

「しらけ」を感じた社員は、
仕事へのモチベーションやパフォーマンスを大きく低下させます。
最悪の場合、そのまま退職につながることも……。
今回の記事では、社員に「しらけ」を感じさせないために必要なことをお伝えします。

社員のモチベーションを上げたいと思った時、
効果的なのは社員が喜ぶ施策ではありません。
本当に必要なのは「働く考え方改革」であり、
仕事に対する意識の変革です。

新人の育成に困っている会社様は多いと思います。
いったいどのような研修及び取り組みが有効なのでしょうか?
今回は実際にあった例をもとに、どんな育成が新人を育てるのか紹介します。

リモートワークが日の目を浴びるようになって、はや数ヶ月。
上手く機能している企業とそうでない企業に分かれ始めています。リモートワークをより効率的にするためには、どのような人事評価を行えばよいのでしょうか。
リモートワークの特質と、そこでの評価項目の決め方についてお話しいたします。

部下とのコミュニケーションは、上司にとって普遍的な悩みです。人事評価のフィードバックでも「部下と何を話したらいいかわからない」という声を多く聞きます。そこで今回は、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、その解決策となる支援ツールを紹介します。

脱・年功序列の実現で最後に必要になってくるのは、人事担当者の「想い」です。社会や顧客への想い、株主への想い、取引先への想い、そして共に働く人への想いがなければ、様々な抵抗に屈して改革は頓挫します。制度を変えて運用に成功している企業とそうではない企業の違いは、その原動力となる人事担当者の想いの強さにあります。総合人事コンサルティングのフォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP )の著者・西尾太が、人事担当者に必要な3つのマインドセットについて解説します。