2018.09.25
求めるものがはっきりしていなければ、何をしても「ブレる人事」になります。
ブレない人事を実現するに、会社が求めるものを人事ポリシーで示しましょう。
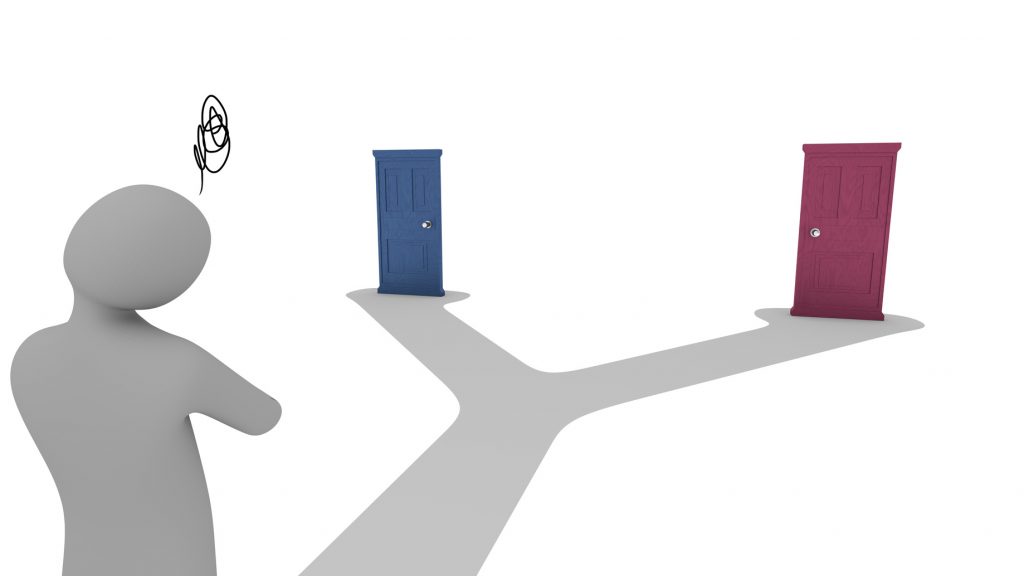
人事の職務は、文字通り「人」に関わること全般です。新しい社員の採用や社員の勤怠管理など多岐に渡りますが、重要な仕事の一つに「社員の育成」があります。育成の内容には社員の研修はもちろんですが、「役職の基準の明確化」や「配属の決定」なども含まれます。
社員の育成と一口に言っても、どのように育成すればいいのか悩む人は多いと思います。社員一人一人にあった育成をし、効率的に成長を促そうとしている人もいるでしょう。しかしその際に、気をつけてほしいことがあります。それは、「人事をブレさせない」ということ。人事がブレてしまうと社員が不満や不安を抱くだけでなく、企業全体が機能しなくなってしまうこともあり得るのです。
1.社員研修
社員育成の現場として最もわかりやすいのは、新入社員の研修ではないでしょうか。新人研修はほとんどの会社で実施されています。それだけ「新人は育成しなければならない」という風潮が根付いている企業は多いということでしょう。しかし、果たしてその研修は本当に社員の成長につながっているのでしょうか?人事がブレていると、社員研修で達成したい目標も漠然としてしまいます。目標がハッキリしていなければ、成長につなげられることはできません。
たとえば、あなたは新人研修で玉ねぎを炒めました。次の研修では、米を研ぎました。その次の研修では、スパイスを調合しました。そこで研修が終わったとしましょう。さて、何がしたい研修だったのでしょうか。そもそも「美味しいカレーをつくるための研修」ということさえ理解せずに研修に参加した社員さえいるかもしません。もし、カレーに関連する研修だと理解していても、この研修だけではいつまでたっても美味しいカレーはつくれません。
そう、研修は目的なくして行うものではないのです。あらかじめ、新入社員に研修の目的、目標を具体的に伝えることで、新入社員はその目的に対し自ら行動をおこします。
具体的な目的のある研修とない研修では、そもそも新入社員の行動がまったく違います。「美味しいカレーを作るための研修」だとわかっているのであれば、玉ねぎを炒めた人はいかに効率的に玉ねぎを炒めるかを追求する、もしくは最終的にカレーになると知っているのであればどのように炒めれば美味しいカレーになるのか分析する――など、行動に移すことができるのです。
研修は新入社員だけでなくベテランや役職に応じて行う場合もありますが、たとえ新人研修でなくても同様です。目的を明確にして初めて、役職に応じやスキルを身につける事ができます。
2.役職の基準
人事の仕事は多岐に渡りますが、ブレる人事が影響を及ぼしやすいのが「役職の基準」の決定です。役職の基準が明確でないと、部長や課長などにふさわしいスキルはないのに、長期間企業にいるからと言う理由で役職がついたり、私情が大きく挟まれたりするなど、不公平な基準が設けられます。明確な基準は、人事の基盤。若手の社員が不満を持ったり、意欲を削がれたりしてしまわないように、基盤はしっかりと整えましょう。

逆のパターンとして、若手のモチベーションの向上を図ろうという目的で若手を抜擢する人事も少なくはありません。
確かに、抜擢された若手社員のモチベーションは上がるでしょう。しかし、他の同僚はどうでしょうか。全員、その社員の抜擢に賛同しているのでしょうか。そもそも、その若手社員は本当に抜擢されるに値する人物なのでしょうか。同じぐらい、もしかしたらもっと優秀な社員がいる可能性はないのでしょうか。
もしその抜擢が、全員が納得いくものではないとしたら、「なんであいつが」といった不満を抱く原因になります。つまり、若手社員を抜擢するのであれば、全員が納得いく人選でなければならないということ。誰が見ても、他の社員より抜きん出た能力を持っていて、なおかつ嫉妬の対象にならない人望の厚い人間でなければならないのです。そうでなければ、他の社員のモチベーションが上がるどころか、離職の原因になってしまいます。
「役職を付与する」というのはとても難しいことです。たとえ最も優秀な社員を管理職にできたとしても、業績が下がり、人が離れるという不利益をもたらす結果になる可能性は低くありません。
漠然とした理由での抜擢や、スキルのない人の抜擢、私情に流される抜擢など、他の社員が不満を抱くような抜擢をしないためには、周囲が役職の基準を理解する必要があります。この役職はどの程度のスキルが求められるのか、どのような条件があるのかなど、より具体的に策定することで、役職の付与自体も私情に流されませんし、周囲を納得させられることもできるでしょう。
3.配属の決定
さらに、配属の決定も人事の担当です。中には社員の意向を最大限に尊重し、要望を聞いたうえで配属先を決定するのが最善策だと考えている人がいると思います。ただ、現実的には難しいから行っている人が少ないだけだと。しかし、本当は、人事担当者が社員に対して「どの部署に配属されたいのか」などを無責任に尋ねてしまうことは良策とは言えません。
例えば、希望部署を尋ねました。しかし、様々な事情によりその希望を叶えられることができず、他の部署への配属にしたとしましょう。このとき、社員は「希望を通す気がないならはじめから聞くな」と不満に思ってしまいます。さらに、他の社員は希望部署に配属されたらどう思うでしょうか。希望部署へ配属されなかった人は、「なんであいつだけ」と不満を抱きます。
このような不満は社内の雰囲気を悪くさせる他、人間関係の悪化につながり、離職や仕事効率の悪化にまで影響しかねません。とはいえ、できる限り社員の希望は知りたいもの。もし社員に希望部署を尋ねる場合は、公正さを明確にし、理解してもらった上で尋ねましょう。希望を叶えられない場合は、しっかりと説明することも大切です。
先述の通り、ブレる人事のもと、研修などが行われてしまうと企業への悪影響は避けられません。では、ブレない人事を行うためにはどうすればいいのでしょうか。
その答えは、人事ポリシーの策定にあります。人事ポリシーは端的に言えば、企業の「人」に対する考え方を明確化したものです。
人事ポリシーの策定はあらゆる人事の職務の基盤となるもので、企業の経営理念と社員のキャリアビジョンの方向性を一致させることができます。そのため、社員に将来のビジョンを見せるほか、社員の育成や評価・待遇の基準を明確にし、あらゆるモノ・コトを見える化します。会社の基盤となるものですので、まずは確固たる人事ポリシーを策定することを目指しましょう。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊
成果主義、職務主義、年俸制、人事部廃止… 90年代から変わらぬ「人事」の構造、変わらぬ平均給与額が、日本を世界トップクラスの「社員が会社を信頼しない国」へと導いたのです。
なぜ変革が進まないのか、その背後に潜む「考え方」の欠如とは何でしょうか?

中学時代に習ったこと、覚えてますか?
多くの人にとっては、すべての勉強の基礎になっている大事な「当たり前」のことですが、思い出せと言われても思い出せる方は少ないでしょう。
この「この一冊ですべてわかる 人事制度の基本」には、人事の当たり前が詰まっています。

ー「なぜ、あの人が?」
なぜ多くの企業で「評価基準」が曖昧になっているのでしょうか。
どうすれば給与が上がるのでしょうか。
11,000人超の人事担当者から絶大な支持を得るコンサルタントが、今まで9割の会社が明かさなかった「絶対的な指標」を初公開!

テレワーク時代には「ジョブ型」に留まらず、「超ジョブ型人事」が不可欠。
その一番の理由は、テレワークをはじめとするこれからの働き方には「監視しない事が重要であるから」です。

人事の“必須科目”を押さえる
プロの人事力
次のステージに向けて成長するためのキホン
人事担当者に必要な知識・学び方、仕事に対する心構え、業務との向き合い方、さらには人事マネージャー、人事部長へとキャリアアップするために必要な能力・スキルを一挙公開

新卒でも、中途入社であっても、人事未経験で人事部に配属されたとしたら、
どのような考え方を持ち、何をして過ごすべきなのでしょうか?
今回は若手人事担当者の心構えについて解説します。

今回は人事担当者が持っておくべき心構えについて、
フォー・ノーツ代表の西尾がお話いたします。
人事部に配属されてまだ日が浅いうちは、目の前の仕事で精いっぱいかもしれません。
そんなときには心構えを思い出して、必要なことを再確認してみて下さい。

新人の育成に困っている会社様は多いと思います。
いったいどのような研修及び取り組みが有効なのでしょうか?
今回は実際にあった例をもとに、どんな育成が新人を育てるのか紹介します。

リストラが増えています。コロナ禍の影響だけでなく、実はそれ以前から70歳までの雇用延長努力義務などを見据えて「黒字リストラ」と言われる施策をとる企業が増えていました。終身雇用や年功序列も終わりを迎えようとしています。40歳を過ぎたら希望退職を勧められてしまうかもしれません。今、求められているのは、いざという時に他にも行ける力です。今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、「どこでも通用する力」を育む、評価基準のつくり方を解説します。

創業したてのベンチャーから成長後期、大企業クラスの規模に至るまで、
会社には様々な変化があります。そしてそれは、人事部も同じ。
今回は各ステージごとの人事部の立ち位置の違いと、
人事が陥りがちなことをお伝えします。

いま再び注目を集めている「ジョブ型雇用」や「成果主義」は決して新しい考え方ではありませんが、これからの働き方を考える中では重要な要素です。 その実現のためにはジョブディスクリプション(職務記述書)が必要とされています。しかし、ジョブディスクリプションの策定や運用には、様々な課題も想定されます。 「働き方」「雇用のあり方」「管理のあり方」「評価のあり方」「給与・処遇のあり方」といった「考え方」そのものをどこまで変えるのか、といったことをよく考える必要があります。 今回は代表西尾から、これからの時代の働き方や評価についてお伝えしていきます。

今再び注目を集める「ジョブ型雇用」や「成果主義」。 決して新しい考え方ではありませんが、これからの働き方を考える中では重要な要素です。これらの導入には、ジョブディスクリプション(職務記述書)が必要ですが、策定や運用には多くの困難が存在します。 今回は代表西尾から、これからの時代の働き方や評価についてお伝えしていきます。

会社にとって社長は意思決定者であり、常に先頭を走り続ける存在です。
それでも、いつでも正しい判断ができるわけではありません。
社長の指示や行動が会社の人事ポリシーに沿わない場合、
自信をもって「待った」をかけられる人事担当者になってください。