日本の労働生産性は、先進国で最低レベル。人事担当者の間でも「うちは生産性が低い」「残業を減らさなきゃ」といった話がよく聞かれます。働き方改革を進める中、生産性を上げるには、人事担当者はどのようなことに取り組むべきでしょうか? そこで今回は、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、労働生産性を上げる方法について解説します。
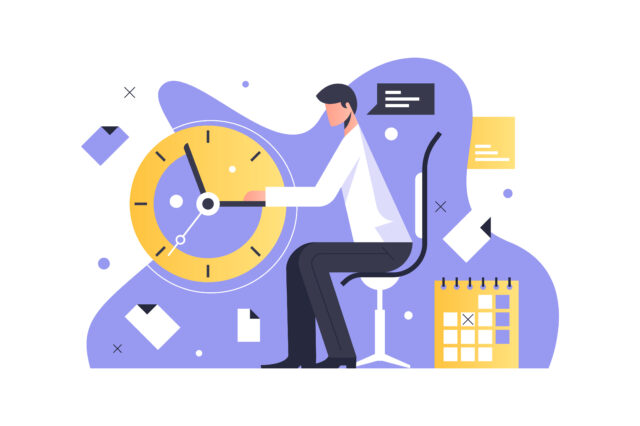
「日本は生産性が低い」と言われて久しいです。時間当たりの労働生産性を比較すると、日本はOECD加盟国35カ国の中で21位にあたり、米国を始めとするG7各国の中では最下位になっています。
ここ数年は、「生産性の向上」「業務の効率化」はビジネスにおける流行語のようになっており、人事担当者の間でも「うちの会社は生産性が低い」「働き方がダメだ」「もっと効率化しないと」といった話をよく聞きます。生産性の向上や業務の効率化は、もちろん重要です。
しかし、「生産性」とは具体的に何を指すのか、実はよくわかっていない人も多いのではないでしょうか。なんとなく感覚的に「生産性を上げろ」「残業を減らせ」と言ったりしていませんか?
総務省の定義では、「生産性」とは、経済的な成果を生み出す効率性を指す概念で、これを定量的に表す指標のひとつとして「労働生産性」が用いられています。労働生産性は、一般に就業者1人当たり、あるいは就業1時間あたりの経済的な成果として計算されます。
人事担当者のみなさんは、自社の「労働生産性」をちゃんと見ていますか?
具体的な指標を追い追いかけていますか?
労働生産性を可視化するひとつの方法として「労働分配率」があります。企業は事業が生み出した付加価値を基に、人件費などの諸費用をまかない利益を得ています。労働分配率は、企業が生み出した付加価値のうち、どれだけ人件費に分配されているかを表します。この数字の推移によって、自社の生産性が可視化され、具体的な施策を打つための手掛かりになるのです。
自社の労働分配率は、簡単に調べることができます。人件費を売上総利益で割ったものが、労働分配率です。以下の数式で計算してみてください。
人件費÷売上総利益=労働分配率
売上総利益とは、いわゆる粗利です。売上総利益の中には販売管理費があり、売上総利益から販売管理費を引くと、営業利益になります。この販売管理費の中に、人件費が含まれています。売上総利益の中で人件費がどれくらい占めているのかが、人事担当者が注目すべきポイントです。
労働分配率は、ご存知の方がほとんどだとは思いますが、単なる知識として終わっていて活用していない人も多いのではないでしょうか。労働分配率の推移を確認し、人件費や人員数の推移をチェックしてみましょう。頭数が増えれば、当然、人件費は増えますが、売上総利益が伸びていれば問題ありません。
労働分配率が低ければ、人件費が占める割合が低い状態で高い付加価値を生み出しているわけですから、「生産性が高い」ということになります。ですから労働分配率は低いほうがいいのですが、これは業種によって異なるため、何%が適切ということは一概には言えません。
ここで重要なポイントは、「人件費」の推移だけを見ても、あまり意味がないということです。人件費が上がっていても、売上総利益が上がっていれば、労働分配率は上がりません。人件費の上昇以上に、売上総利益が上昇していれば、何の問題もないのです。
ところが、人件費が上がっているだけで「やばい」「うちは生産性が低い」「残業を減らさなきゃ」と慌ててしまう人が少なくありません。これはまったく意味のないことで、たとえ人件費が増えていても、売上総利益が伸びているのなら、生産性は上がっているのです。
本当に「やばい」のは、売上総利益が変わらないのに、または下がっているのに、人件費が伸びている状態です。これは労働分配率が上がり、生産性が下がっている状態ですから、対策を講じなくてはなりません。
労働分配率は、本来であれば、経営や経営企画が見ていればいいのですが、意外と会社の中でも誰も見ていなかったりします。私の前職でも、誰ひとり指摘していた記憶がありません。労働分配率を聞かれてすぐに答えられる会社は、ほとんどないのではないでしょうか。人事はもちろん、社長でさえ危ないです。
「生産性を上げろ」「業務を効率化しろ」と号令を出す前に、何を持って「生産性」としているのか、まずはそこを明確にすることが必要です。
労働分配率の推移をマクロ的に捉えて、次に同業他社や近しい業種の労働分配率を見てみましょう。上場企業の有価証券の報告書を見れば、一発でわかります。他社の有価証券を見て、自分の会社の労働分配率は他社と比べて高いのか低いのか、チェックしてみてください。
そして、自社の労働分配率が高ければ、その原因は何か、残業が多いのか、賞与の支給が多いのか、他社と比べて給与が高いのか、具体的な要因を探っていきます。
たとえば、労働分配率が高い原因が「他社より平均年齢が高い」ということであれば、年功序列で社員の給料が高くなっていることから、労働分配率が上がっていると考えられます。となれば、人事制度の見直しが急務です。「人件費を抑えないと、いい加減まずいな」というスイッチを入れるためにも、人事担当者は労働分配率の推移を確認しておく必要があります。
生産性を確認する指標は、ROA(総資産利益率)やROE(自己資本利益率)などいろいろありますが、自社と他社の労働分配率を比べてみるだけで十分だと思います。
人件費の中身をチェックし、労働分配率が高くなっているのは、社員の人件費なのか、アルバイトの人件費なのか、定期的な人件費なのか、変動費的な人件費なのか、といったところを細かく掘り下げていけば、正社員を減らしてアルバイトを増やしていこうとか、正社員が残業するよりアルバイトを入れたほうがいいといった施策が見えてきます。
たとえば、アルバイトが時給1200円で、正社員が時給2000円だとしたら、正社員が残業をしたら1.2倍の時給2400円ですから、時給1200円のアルバイトを入れたほうが生産性は上がります。
自社の労働分配率を調べることで、こうした具体的な施策に入っていけます。「誰の人件費が多いんだっけ?」とか、部門別や事業別に掘り下げていくと、いろんなことが見えてきます。
たとえ残業が多い部署があっても、労働分配率が低ければ、生産性は高いのです。この部署の残業を減らすことによって、会社全体の生産性が下がってしまうかもしれません。多少は残業が多くても、健康を害するほどの時間でなければ、「働きすぎに気をつけてくださいね」と言うだけでもいいわけです。
逆に、労働分配率が高いのにやたらと残業をしている部署があったら、これは当然、注意が必要でしょう。
一律に「残業を減らせ」と言うのは簡単ですが、人事担当者はそういうところまで踏み込まなくてはいけないのではないでしょうか。労働分配率を普段から見ておけば、適切な人事施策を打つことができます。人事担当者のみなさんが、労働分配率の推移をチェックして、生産性の向上に努めていきましょう。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊
成果主義、職務主義、年俸制、人事部廃止… 90年代から変わらぬ「人事」の構造、変わらぬ平均給与額が、日本を世界トップクラスの「社員が会社を信頼しない国」へと導いたのです。
なぜ変革が進まないのか、その背後に潜む「考え方」の欠如とは何でしょうか?

中学時代に習ったこと、覚えてますか?
多くの人にとっては、すべての勉強の基礎になっている大事な「当たり前」のことですが、思い出せと言われても思い出せる方は少ないでしょう。
この「この一冊ですべてわかる 人事制度の基本」には、人事の当たり前が詰まっています。

ー「なぜ、あの人が?」
なぜ多くの企業で「評価基準」が曖昧になっているのでしょうか。
どうすれば給与が上がるのでしょうか。
11,000人超の人事担当者から絶大な支持を得るコンサルタントが、今まで9割の会社が明かさなかった「絶対的な指標」を初公開!

テレワーク時代には「ジョブ型」に留まらず、「超ジョブ型人事」が不可欠。
その一番の理由は、テレワークをはじめとするこれからの働き方には「監視しない事が重要であるから」です。

人事の“必須科目”を押さえる
プロの人事力
次のステージに向けて成長するためのキホン
人事担当者に必要な知識・学び方、仕事に対する心構え、業務との向き合い方、さらには人事マネージャー、人事部長へとキャリアアップするために必要な能力・スキルを一挙公開

人事にとって「離職」は悩みの種の1つです。採用難に加えて「定着せずに辞めてしまう」という課題が、人手不足をますます深刻にしています。離職率が高いのは、いわゆるブラック企業に限りません。近年はホワイト企業であっても辞める若手が増えています。その根本的な原因を探ってみましょう。

人事担当者が覚えておくべき心構えにはどんなものがあるのでしょうか?
今回は社員とどのように向き合っていけばいいのか、フォーノーツ代表の西尾がお話しします。

経営陣から下りてくる人事施策が果たして本当に人事ポリシーに則っているのか?
それを判断するのは人事の役目です。
そのために必要な「人事の人事ポリシー」とは?

人事異動を拒否する人が稀にいます。拒否するにはそれなりの理由があるはずです。人事部はどのように対応したらいいのでしょうか? 今回は「人事異動」シリーズ第2回。『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、人事異動を拒否された際の正しい対処法について紹介します。

働き方改革を推進している現代社会において、いまだにブラックと言われる企業がなくならないのはなぜでしょうか?労働環境を整えるのは、人事の重要な課題です。そこで今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、ブラック企業について改めて問い直します。

バブル崩壊後、企業は採用を抑制し、ジョブ型雇用に切り替えようと試みました。
しかしその試みが上手くいった企業は少ないのが現状です。
ジョブ型雇用が注目を集める昨今、
会社は過去の教訓を活かしどのように動くべきなのでしょうか?

金融業界を中心に、「通年採用」を採用しはじめた企業が登場しはじめた2020年。ニュースでも世の中を大いに賑わせ、注目を集めました。さて、この「通年採用」は、今までの採用制度とどう違うのでしょうか?また、通年採用は、採用力に影響はあるのでしょうか?「通年採用」を行ううえで押さえておかなければならない大事なポイントは何でしょうか?今回は、「通年採用」の効用について、お話しします。

JBpressにてビジネスパーソン向けのWebコラムを12月11日(水)よりスタートいたしました。