2019.06.10
人事担当者が持つ人事のお悩みは、なかなか共有することも難しいため、
自分の(あるいは部署内の)力で解決しなくてはならないことも多いでしょう。
今回は、人事1年目から人事としてキャリアアップしたい人まで、
多くの人事担当者に読んでいただきたい本を3冊ご紹介します。
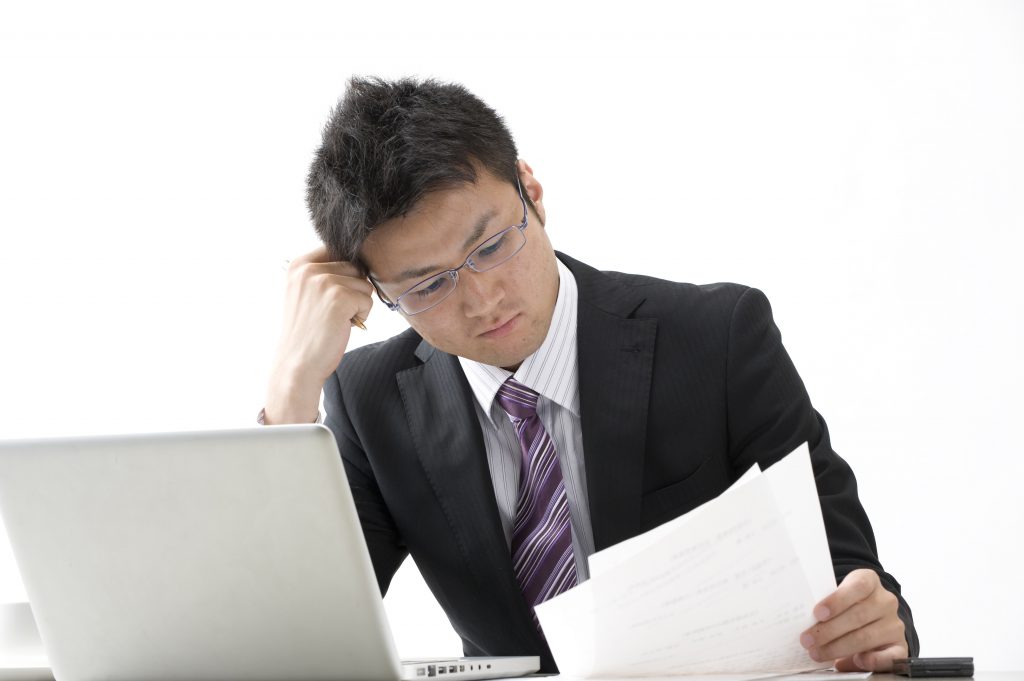
研修、育成、採用、配置…人事担当者が持つ悩みは尽きることがありません。中には、明確な指標がなく、手探りで進めなければいけない人事施策にやきもきしている方もいることでしょう。
実際、人事という仕事はあまり周りに理解されないものです。「プライドの高いエリート集団」「事務作業ばっかりやっていてなんだか暗い」「経営陣の顔色ばかり伺っていて現場の声は無視」・・・そのようなイメージを持っている人も少なくありません。
その状態で前述のような手探りの人事施策を打ち出しても、効果が出ないばかりか、社内の雰囲気や社員のモチベーション、人事に対する印象がますます悪化していく可能性があります。
では、人事担当者はどのように人事施策を進めていけばよいのでしょうか?
どうすれば、人事への好印象を持ってもらえるのでそうか?
そしてどうすれば、現場にも経営陣にも頼りにされるようになるのでしょうか?
その答えを探す際に助けとなる書籍をフォー・ノーツ株式会社代表 西尾太の著作3冊をご紹介しましょう。
まずご紹介したいのは、この1冊です。
人事の超プロが明かす評価基準 (単行本) 西尾 太
「あの人より自分の方が頑張っているのに、なぜ評価されないのか?」
「係長、課長、部長、と昇進していくために必要なスキルは?」
など、評価する側だけでなく、評価される側も知っておきたいことをまとめました。
世の中には様々な業種の企業があります。小売店や飲食店のような店舗を構えている企業もあれば、社員が一日中パソコンの前に座って作業をしている企業もあります。だから、「評価の基準はこういうものだ」と一概には言えず、企業によって特色があるものである。意識的に、あるいは無意識的にそう考えている方は少なくないでしょう。
しかし、根本にある評価制度の概念は、非常にシンプルで、全ての企業に共通しています。人事担当者はどのような意識を持ちながら、評価制度を策定し、評価しなければならないのか。評価される側の社員は、どのようにキャリアプランを設計していけばよいのか。全社員に共通するお悩みに対するヒントが満載で、すべてのビジネスマンにお手に取っていただきたい1冊になっています。
働き方が変わる、会社が変わる、人事ポリシー 西尾 太
次にご紹介するのは、こちらの1冊です。
この章の題としても掲げさせていただきましたが、あなたは自社の「人事ポリシー」をすぐに答えられるでしょうか?どのような人材が自社に必要で、どのような待遇を持って迎え、どのように育成し、どのように評価をすればよいかが明確でしょうか。ぱっと答えられる方はそれほど多くないでしょう。
人材の定着率や採用などのお悩みは、もしかしたら「明確な人事ポリシーがないこと」が原因かもしれません。人事ポリシー策定のためには、ぜひ「働き方が変わる、会社が変わる、人事ポリシー」をご活用ください。人事ポリシーの重要性や、どのように策定すればよいかなど、詳しく解説しています。この本はいわば、人事のガイドブックです。
外から見れば華やかな印象を持たれがちな人事ですが、中には「人事は地味でつまらない、面倒くさい仕事」だと感じている人事担当者もいることでしょう。そのような方の意識を変える1冊になると思います。ぜひ、人事に携わる方には一度目を通していただきたいですね。
最後にご紹介するのは、こちらです。
プロの人事力 西尾太
2019年3月に出版されたばかりの最新著書になります。
人事担当になって1年目、右も左もわからない。どのように勉強すれば良いかわからない。そのような方に送る、人事のいろはから学び方、心構えまで、人事に必要な要素を網羅した1冊です。
先程、人事の印象は華やかな印象を持たれがちと申し上げましたが、それは採用や配置、研修の担当といった多くの社員の目に見える範囲内の話です。蓋を開けてみれば細々とした作業や現場との気が重い調整など、あまり楽しいとは言えない仕事もあるでしょう。そのような業務に対してどうやって向き合っていけばよいのか、そして社内でどのようなポジションを築いていけばいいのかなど、地に足をつけた人事担当者になるための知識が詰まっています。
また、人事の中でステップアップしていくために必要な能力やスキルについても解説しています。人事1年目だけでなく、役職を持つぐらい活躍されている方にも読んでいただきたいですね。
完璧な人間がいないように、完璧な人事施策というものは存在しません。誰かを立てれば誰かが割を食うことを踏まえながらも、人事施策を進めなければいけない立場にいるのが人事担当者です。ただし、一人でも多くの人に納得してもらえるように進めなければならないのは言うまでもありません。今回ご紹介した3冊を理解を得るための礎にしていただけましたら幸いです。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊
成果主義、職務主義、年俸制、人事部廃止… 90年代から変わらぬ「人事」の構造、変わらぬ平均給与額が、日本を世界トップクラスの「社員が会社を信頼しない国」へと導いたのです。
なぜ変革が進まないのか、その背後に潜む「考え方」の欠如とは何でしょうか?

中学時代に習ったこと、覚えてますか?
多くの人にとっては、すべての勉強の基礎になっている大事な「当たり前」のことですが、思い出せと言われても思い出せる方は少ないでしょう。
この「この一冊ですべてわかる 人事制度の基本」には、人事の当たり前が詰まっています。

ー「なぜ、あの人が?」
なぜ多くの企業で「評価基準」が曖昧になっているのでしょうか。
どうすれば給与が上がるのでしょうか。
11,000人超の人事担当者から絶大な支持を得るコンサルタントが、今まで9割の会社が明かさなかった「絶対的な指標」を初公開!

テレワーク時代には「ジョブ型」に留まらず、「超ジョブ型人事」が不可欠。
その一番の理由は、テレワークをはじめとするこれからの働き方には「監視しない事が重要であるから」です。

人事の“必須科目”を押さえる
プロの人事力
次のステージに向けて成長するためのキホン
人事担当者に必要な知識・学び方、仕事に対する心構え、業務との向き合い方、さらには人事マネージャー、人事部長へとキャリアアップするために必要な能力・スキルを一挙公開

「しらけ」を感じた社員は、
仕事へのモチベーションやパフォーマンスを大きく低下させます。
最悪の場合、そのまま退職につながることも……。
今回の記事では、社員に「しらけ」を感じさせないために必要なことをお伝えします。

リモートワークが日の目を浴びるようになって、はや数ヶ月。
上手く機能している企業とそうでない企業に分かれ始めています。リモートワークをより効率的にするためには、どのような人事評価を行えばよいのでしょうか。
リモートワークの特質と、そこでの評価項目の決め方についてお話しいたします。

社員の育成というと「研修」を思い浮かべる方が多いですが、
実は研修よりも効果的な育成方法があります。
それは、現場を理解した上での評価制度の策定及び改善です。

新型コロナウイルスの影響によって消費が落ち込み、飲食店やショッピングモールなどの営業自粛も相まって、業績が低迷している企業が増えてきました。 こうした緊急事態、かつ長期戦が見込まれる時こそ、企業は数年後の展望を見据えた事業戦略を立てることが大事です。 こうして立てられた事業戦略をもとに今後の人事戦略を考えていきましょう。

金融業界を中心に、「通年採用」を採用しはじめた企業が登場しはじめた2020年。ニュースでも世の中を大いに賑わせ、注目を集めました。さて、この「通年採用」は、今までの採用制度とどう違うのでしょうか?また、通年採用は、採用力に影響はあるのでしょうか?「通年採用」を行ううえで押さえておかなければならない大事なポイントは何でしょうか?今回は、「通年採用」の効用について、お話しします。

転職市場が活性化している昨今、「出戻り制度」を設ける会社が増えています。
しかし、人事担当者は安易にこうした制度に飛びついてはいけません。メリットとデメリットを理解して判断することが重要です。

労務分野の法律や制度に関する「お勉強」が
人事担当者の第一歩だと勘違いしてしまっている方は少なくありません。
しかし実は、人事担当者には専門的な知識など必要ないのです。
この記事では人事担当者に求められる知識を解説していきます。

キャリアステップが必要なのはわかるけど、
どのタイミングで導入するべきかわからない。
今回はこの疑問に、フォー・ノーツ株式会社の曽根がお答えいたします。