2018.10.23
フォー・ノーツ代表の西尾が、
人事3年目の社員に求められる3つのことを紹介していきます。
1年目は仕事を理解し、2年目はできたところ、できなかったところを洗い出す。
これらを踏まえて臨む3年目には、いったい何が必要なのでしょうか?

今日は人事3年目の皆さんは何をすべきか、何を学ぶべきかということをお伝えしましょう。
人事3年目を迎えたら、当然のことながら自身の作業ではなく、一つのユニットを意識してほしいと思います。例えば、給与担当であれば、自身が課長ではなくても周りの仕事を見渡してみて下さい。自分の仕事の前工程、そして自分の工程、後工程をどう変えていくのか、改善していくのか。
今のままでいい、ではなく「改善していく」という目線を持てるようにするといいですね。
例えば、給与計算が自分の担当している領域であれば、給与領域全体。
人事の構成は大まかに分けると、「配置と採用」「給与厚生(勤怠管理や福利厚生、チアガール、夏まつり、新春パチンコ大会などのイベント企画)」「育成評価」といった組織で成り立っているのが一般的です。
そのオペレーションのユニットを意識し、どこをどう直していくか、ということです。だって、ずっと人事にいるのであれば、1年目で自分の仕事を覚えているでしょう? 1年目はやっと仕事をこなし、2年目でどこに何の課題が多かったか、あらかじめできなかったことは何か、何を変えると改善できるのかを意識する。3年目は実際にそれを改善するフェーズです。そういった景色を見るようにしましょう。
人事は、人事だけやっているよりも営業や工場などの現場も経験したほうがいいです。なので、このくらいの年次で、一度違う部署に行けるとなおいいと思います。
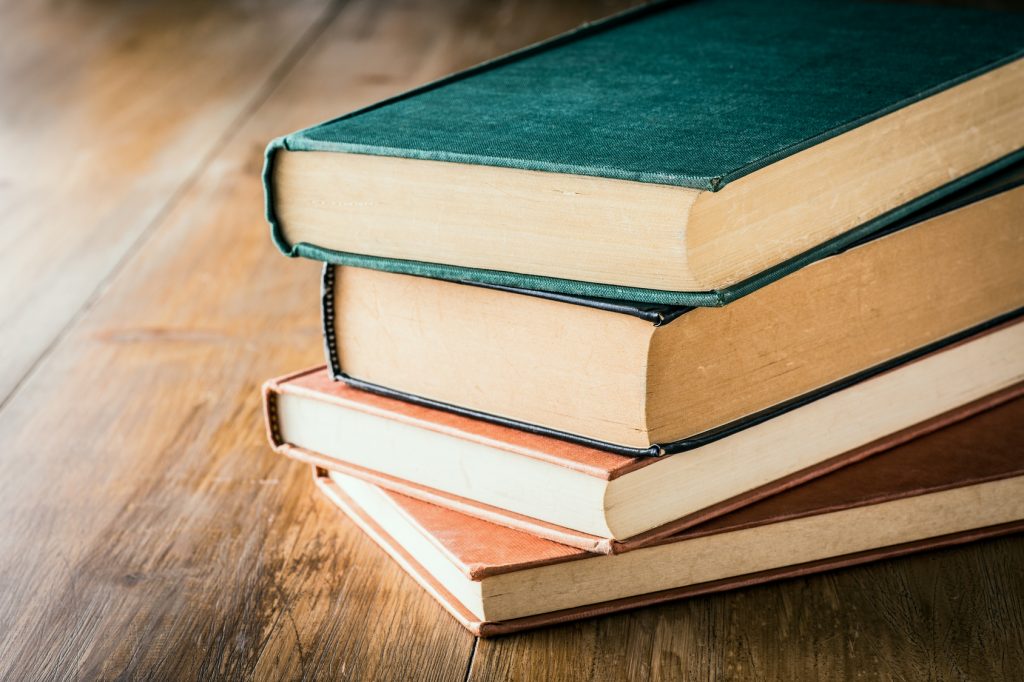
1年目から3年目、駆け出し人事のころは仕事に関する本をひたすら読んで下さい。まずは労働法規から。薄いのでいいから、人事に関連しなくても読んだほうがいい。新聞も読んだほうがいいですね。
よく「家で勉強します」なんて言う人がいるけど、なかなかやれないですよね。私だってやらないです(笑)。通勤時間とか、隙間時間を活用して勉強することが大切です。
本で読んだことは、きっちり仕事に活かすようにしましょう。
例えば、PDCAについて。マネジメントとは、PDCAを回していくことです。人事の3年目は概念を知り、自分の仕事のPDCAを回せるようになって下さい。明確な目標を立てて、しっかりした計画をたてて、段取りを組んでいつまでに何をやる。進捗が遅れていたら修正する。
他人に「いつまでにやってね」と言って任せていてもだめですよ。自分でプランニングするんです。
そろそろ、企画を提案することも増えてくるでしょう。図解化、物事と物事の関連を示す、全体像を把握する――。そのために、マインドマップとかそういうツールもありますね。知っておいたほうがいいでしょう。
こうした「型」を身に着けるか否かで、仕事の進めやすさは大きく変わってきます。ロジカルシンキング、企画提案、プレゼンテーションなどは定型化されているスキルですから、ぜひ3年目くらいまでに学んでおいてください。
例えば、採用であれば、会社説明会でプレゼンするというのはもう必ず決まっている訳です。でも、パワポを映してその画面を見ながらしゃべっている人もいるんだよね。「お前誰に向かってしゃべってるんだ、スクリーンか!」と思う訳ですが(笑)、プレゼンテーションスキルをいったん頭の中に入れておけば、そんなことはしなくなるはずなんです。
ロジカルシンキングという、物事を構造的に見る、俯瞰してみる学問もあります。このあたりも、3年目で知っておくとだいぶ変わります。
3年目の人は、こうした人事以外の勉強も積極的に始めたほうがいいですね。異動で経験させてもらえるならばそれでもよいでしょう。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊
成果主義、職務主義、年俸制、人事部廃止… 90年代から変わらぬ「人事」の構造、変わらぬ平均給与額が、日本を世界トップクラスの「社員が会社を信頼しない国」へと導いたのです。
なぜ変革が進まないのか、その背後に潜む「考え方」の欠如とは何でしょうか?

中学時代に習ったこと、覚えてますか?
多くの人にとっては、すべての勉強の基礎になっている大事な「当たり前」のことですが、思い出せと言われても思い出せる方は少ないでしょう。
この「この一冊ですべてわかる 人事制度の基本」には、人事の当たり前が詰まっています。

ー「なぜ、あの人が?」
なぜ多くの企業で「評価基準」が曖昧になっているのでしょうか。
どうすれば給与が上がるのでしょうか。
11,000人超の人事担当者から絶大な支持を得るコンサルタントが、今まで9割の会社が明かさなかった「絶対的な指標」を初公開!

テレワーク時代には「ジョブ型」に留まらず、「超ジョブ型人事」が不可欠。
その一番の理由は、テレワークをはじめとするこれからの働き方には「監視しない事が重要であるから」です。

人事の“必須科目”を押さえる
プロの人事力
次のステージに向けて成長するためのキホン
人事担当者に必要な知識・学び方、仕事に対する心構え、業務との向き合い方、さらには人事マネージャー、人事部長へとキャリアアップするために必要な能力・スキルを一挙公開

経営陣から下りてくる人事施策が果たして本当に人事ポリシーに則っているのか?
それを判断するのは人事の役目です。
そのために必要な「人事の人事ポリシー」とは?

創業したてのベンチャーから成長後期、大企業クラスの規模に至るまで、
会社には様々な変化があります。そしてそれは、人事部も同じ。
今回は各ステージごとの人事部の立ち位置の違いと、
人事が陥りがちなことをお伝えします。

他の職種と同じように、人事担当者にも勉強は必要です。
とはいうものの、きちんと勉強している人事担当者が少数派というのもまた事実。
まずは通勤などの隙間時間でいいので、勉強習慣を始めてみませんか?

近年、メンタルヘルスが引き金となった深刻なトラブルが相次いでいます。会社の責任で「うつ病」などの精神疾患になってしまった社員がいた場合、人事はどのように対応をしたらいいのでしょうか? そこで今回は、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、人事担当者が知っておくべきメンタルヘルスの対処法について解説します。

テレワークやDX対応、ジョブ型、70歳定年、早期退職、黒字リストラなど、今、人事の課題は山積みになっています。この「第4次人事革命」において、人事担当者がやるべきことは何なのでしょうか? そこで今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、日本企業の人事施策の変遷を振り返りながら、歴史から学ぶべきことをお伝えします。

人事は、人員計画・配置・採用・給与・厚生・育成・評価といった分野と、それぞれに戦略、企画、運用、オペレーションという機能があり、幅広い分野の領域に関わる職種です。一領域の人事担当者からマネジャー、人事責任者になるには、何をどのように学べばいいのでしょうか?本記事では、担当者レベルから人事責任者を目指すために重要なポイントを「人事の学校」主宰・西尾太が解説します。

テレワークの普及、副業の推進、社員の個人事業主化、AIやRPAの活用――。働き方もキャリアプランも多彩になってきたアフターコロナの時代、「正社員」も「雇用契約」もすでに過去の遺物になろうとしています。そこで今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、多様化するワークリソースの活用方法についてお伝えします。

コロナ禍で黒字リストラが増える中、従業員シェアやワークシェアリングなどの雇用を守る取り組みが注目されています。どちらも有効な施策ですが、長期的に継続するかどうかが鍵となります。そこで今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、雇用を守るために人事担当者がすべきことについてお伝えします。