2019.03.22
社員の育成に欠かせないキャリアステップ。
しかしいざ策定するとなると
何から始めればいいのかわからないのではありませんか?
そこでキャリアステップ策定の方法や意識しておいてほしいことを、
前後編に分けてご紹介します。
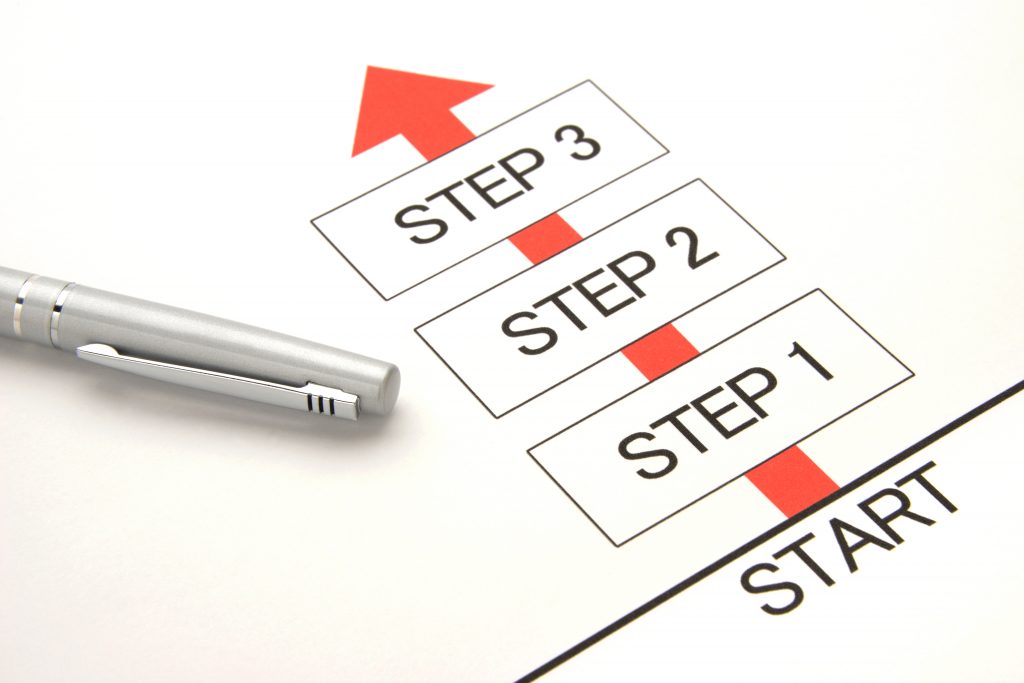
2回にわたってお伝えしている「キャリアステップを策定するときに意識しておきたいこと」。前編はキャリアステップとはいったい何なのかと、キャリアステップに対する心構えについてお話ししました。
前回の記事はこちら
今回はいよいよ、キャリアステップを策定する方法についてお話していきます。前回同様、多くの会社で応用できるように個別具体的な事柄には触れていません。まだ作っていない、あるいは制度はあるものの上手く現場に馴染んでいないという場合には、今回お伝えすることを持ち帰って、策定や検証の土台にしてください。
「キャリアステップの策定は新しいことではなく、今までの社員育成の延長線上にある」
このことが理解できたら、キャリアステップの策定にあたりまずやるべきことが見えてくると思います。それは、「現状の把握」です。キャリアステップが現在の社員育成の延長線上にあることを考えれば、スタート地点である「現在」をしっかりと調べ、把握することは当たり前の話でしょう。
現状を把握するためのチェックポイントを、例としてあげてみましょう。
・経営層はどのような仕事をしているのか
・経営層の仕事をこなすためにはどのようなスキルや考え方が必要か
・そのスキルや考え方を身に着けるにはどのような経験が必要か
・中堅層はどのような成果を求められているのか
・その中でもトップパフォーマーと呼べる社員たちに共通しているものは何か
・社員のパフォーマンスが上がらないのにはどのような原因があるか
・新人が次のステップに進むためには何が必要か
今まで精査してこなかっただけで、ほとんどの会社には社員育成に関する独自の判断基準やノウハウが存在するはずです。まずはそれらを言葉にするところから始めてみてください。すると、今まであやふやだった「会社は社員に何を求め、どう成長してほしいと考えているか」が、一つの流れとなってはっきり見えてくるでしょう。これがキャリアステップのひな型です。
並行して、年次何年目にはこのくらいのポジションについていてほしい、といったことも考えてみてください。最もわかりやすいのは新卒で入社した社員をモデルケースにすることです。22歳で会社に入社して、何年後には○○、その何年後には△△、40代までには最低でも××まではいってほしい、という感じです。
この2つが、キャリアステップの策定において欠かすことができないとても大事な要素となります。「現在の会社がそれぞれのポジションの社員に対して何を求めているか」「大体何歳までにどのポジションにいてほしいか」の両輪で、キャリアステップを考えてみてください。
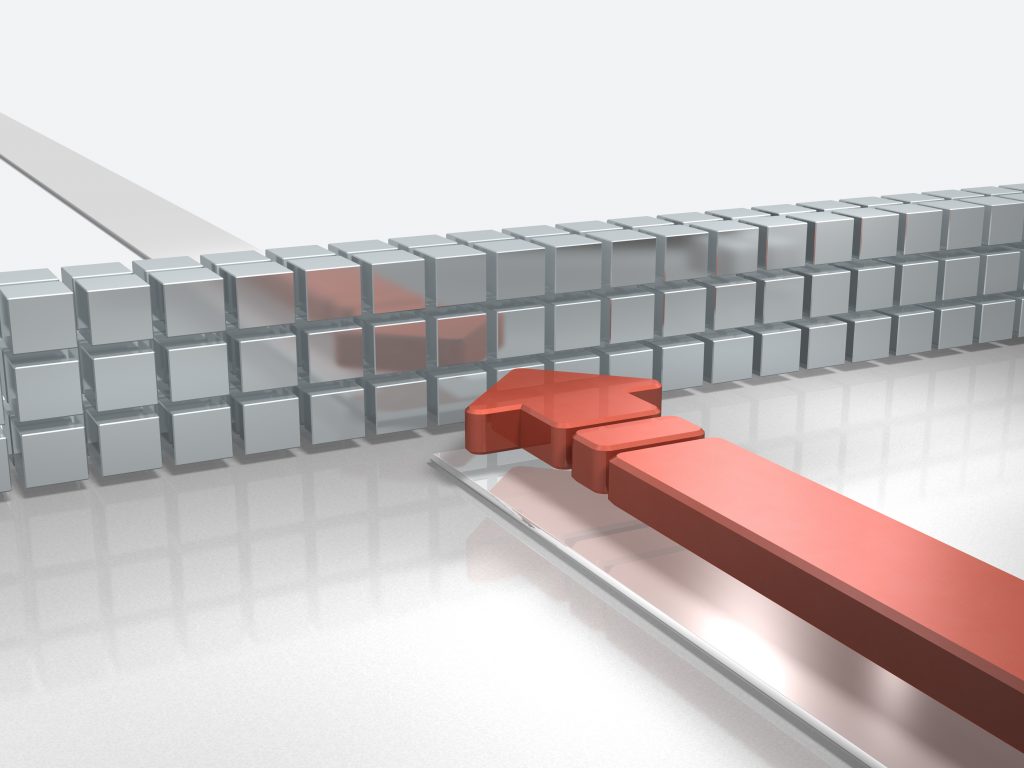
ここまでは現状を洗い出しただけ、つまり下準備です。次のステップでいよいよ人事制度としてのキャリアステップを策定していくことになるわけですが、ここで指標となるのが、「滞留層の出現」です。
「会社が社員に求めること」と「何歳までにどのポジションにいてほしいか」を考えることで、社員の成長に関する大まかな流れは見えてきたと思います。しかし、それはあくまでも理想形。例えばキャリアステップ上のゴールが経営戦略に関わるポジションだとしても、それを実践できる社員はごくわずかでしょう。多くの社員は必ずどこかの段階で壁にぶつかり、それ以上の成長を目指さなくなってしまいます。
また、いくら会社から求められているからといって、全員が素直に応じるとも限りません。会社が全員にコア人材となることを求めても、「自分の時間を大事にしたい」とオペレーティングマネージャーより上のポジションを目指さない社員も一定数いるはずです。
こういった「成長の壁」や「自主的なゴール」が現れる箇所は、多くの社員で共通しています。部長クラスへの昇格が厳しいためにその一歩手前でくすぶっている社員が多かったり、マネージャーで満足してそれ以上の成長を望まなくなる社員が増えたりするのはこのためです。そしてこういった社員たちが、そこより上を目指さない「滞留層」となります。
ただし、滞留層はネガティブな存在ではありません。コア人材として会社が求める人数はごくわずかです。逆に、滞留層がないと人数が必要な現場にマンパワーがなくなるので、よほどの少数精鋭企業でない限りは、会社が回らなくなります。
さて、こういった滞留層がどこにできるかをあらかじめ見抜くことができれば、そこを起点にキャリアステップを策定することができます。例えば滞留層のポジションには多くの社員がつくことが予想されますから、等級や給料を高く設定しすぎると会社が持たなくなってしまいます。また、滞留層ということは会社の一般的な水準と近しいわけですから、「何歳までにはこのポジションに行ってほしい」ということの目安にもなります。
「材料を集めたはいいけど、どこからキャリアステップを策定していけばいいかわからない!」そんなときには、滞留層を指標にしてその前後を埋めていく形で作っていくと、体系的で有用なキャリアステップができ上がりますよ。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊
成果主義、職務主義、年俸制、人事部廃止… 90年代から変わらぬ「人事」の構造、変わらぬ平均給与額が、日本を世界トップクラスの「社員が会社を信頼しない国」へと導いたのです。
なぜ変革が進まないのか、その背後に潜む「考え方」の欠如とは何でしょうか?

中学時代に習ったこと、覚えてますか?
多くの人にとっては、すべての勉強の基礎になっている大事な「当たり前」のことですが、思い出せと言われても思い出せる方は少ないでしょう。
この「この一冊ですべてわかる 人事制度の基本」には、人事の当たり前が詰まっています。

ー「なぜ、あの人が?」
なぜ多くの企業で「評価基準」が曖昧になっているのでしょうか。
どうすれば給与が上がるのでしょうか。
11,000人超の人事担当者から絶大な支持を得るコンサルタントが、今まで9割の会社が明かさなかった「絶対的な指標」を初公開!

テレワーク時代には「ジョブ型」に留まらず、「超ジョブ型人事」が不可欠。
その一番の理由は、テレワークをはじめとするこれからの働き方には「監視しない事が重要であるから」です。

人事の“必須科目”を押さえる
プロの人事力
次のステージに向けて成長するためのキホン
人事担当者に必要な知識・学び方、仕事に対する心構え、業務との向き合い方、さらには人事マネージャー、人事部長へとキャリアアップするために必要な能力・スキルを一挙公開

社員の離職を食い止めるために重要な要素である「臨場感」。
今回の記事では「臨場感とはいったい何なのか」「どうして臨場感が離職を防ぐのか」
を解説していきます。

人事制度の中でも人気のある「研修」。
自社の弱いところにピンポイントで対策ができるので、重宝されていますよね。
しかし研修は実施すればそのまま成長につながるわけではありません。
しっかりと考えないと、研修が様々な無駄を生むもとになってしまいます。

若手・中堅クラスの社員に、会社はいったい何を求めているのでしょうか?
会社が求めているものを知れば、あなたの評価も上がるはずです。

社員のモチベーションを上げたいと思った時、
効果的なのは社員が喜ぶ施策ではありません。
本当に必要なのは「働く考え方改革」であり、
仕事に対する意識の変革です。

企業が新たな人材を獲得する方法には大きく分けて、新卒採用と中途採用の二つがあります。各々の特徴について、ご自身のイメージを持たれているのではないでしょうか。ですが今一度、これからの時代に合った人材採用の考え方を考えていきましょう。 また、コロナ禍における新卒採用の捉え方についてお話しいたします。

1年間で退職した人の割合を表す離職率。「離職率が高い=悪い会社」「離職率が低い=良い会社」と言った認識が世間では一般的になっていますが、果たして本当にそうでしょうか。 実は、離職率だけをみて、その会社の良し悪しを判断することは非常に危険です。 重要なのは離職率の「数字」ではなく、「どんな人が辞めているのか」という離職率の「中身」です。 今回は、人事担当者として「離職率」というテーマとどう向き合い対応するべきなのかをお話しします。

人事ポリシーとは会社の「人」に対する考え方を表明したものです。
会社が抱える「人」の悩みの大半は、社員との間にある意識のミスマッチが原因です。
自社に即した人事ポリシーによって意識をすり合わせることができれば、
複数の課題が一気に解決することも珍しくありません。

人事1年目について、フォー・ノーツ代表の西尾がお話します。
1年目というのは、仕事についてもまだまだ分からないもの。
新人の人事は何をして、どんなことに気を付けるべきなのでしょうか。