2018.11.06
新人の育成に困っている会社様は多いと思います。
いったいどのような研修及び取り組みが有効なのでしょうか?
今回は実際にあった例をもとに、どんな育成が新人を育てるのか紹介します。

組織がある程度大きくなると、新卒採用を考える企業様が多くなります。ただし、新卒採用には様々な課題が存在することを忘れてはいけません。中でも一番大きなものは、「育成」ではないでしょうか?実際、多くの企業様が「どうやって一人前に育てるのか」とご相談にいらっしゃいます。
新人の育成、というとOJTや座学、ジョブローテーションなど、新人研修と呼ばれるものが一般的です。確かにこういった研修にも効果はあるのですが、新人育成においてはもっと重要なことがあります。それは、会社全体の「育成ムード」です。
今回はお客様が実際に導入して、会社全体に育成ムードを醸成させることに成功した施策をご紹介いたします。もちろんすべての企業様で成功するわけではありませんが、参考にしてみてください。
この企業様が実施されたのは、育成担当者を決めて新人育成を任せる、というものでした。新人育成を任せる、といっても研修を全てやってもらおう、というようなことではありません。担当者一人につき新人何人というのを決めて、担当している新人の成長をサポートするイメージです。
実際、やることは
・一年間の目標を決める
・四半期ごとに、目標に対してどんな取り組みをしているか確認する
・一年たったら総仕上げとして成長の成果をプレゼンする
といったものです。
この制度のいいところは、最初に目標を一緒に決めるということと、最後に成長をプレゼンするというところ。
やはり新卒で入った新人であっても、会社が求めるコンピテンシーは存在します。それに気付かせるためにも、そして本人のモチベーションのためにも、目標というのは欠かせません。ここで高すぎず低すぎず、求められるコンピテンシーに沿った目標を立てさせられるかは、育成担当者の腕の見せ所です。
最後に、最初に立てた目標に対して自分がどんな努力をして今どんな姿になっているのかをプレゼンします。この企業様が取り入れたのは、プレゼンの場に社長以下役員を含めた全社員を集めるということでした。
普通に会社勤めをしていて、社長に向かって直接プレゼンする機会などそうはありません。育成担当者だけでなく、新人にとってもいい経験になることでしょう。こちらの方が気合も入ることですしね。
さらにこのプレゼン、翌年度の人事担当者へのプレッシャーにもなります。あらかじめ次の育成担当者を決めておけば、主体的にプレゼンを聞きながら、いろいろなことを考えると思います。
「今度入ってくる新卒には、こういう目標を立てさせればいいのか」「今回は途中で一回伸び悩んだ時期があるみたいだから、自分の番になったら注意してみてみよう」などなど。と同時に、こんなことも感じるはずです。「どうせすぐにやめてしまうとおもっていたけど、きちんとここまで成長させられるんだなぁ」。
これは新人育成にあまり目を向けてこなかった企業様にありがちなのですが、新卒が数年たつと半減してしまうような状態が続くと、「どうせすぐやめるから」と本来指導するべき上司や先輩がまともに向き合わなくなってしまいます。実際に一年間で成長を遂げた新人を見ることで、「自分もここまで育て上げないといけない」というプレッシャーを感じるとともに、「やれば出来るんだ」ということも実感できるんですね。
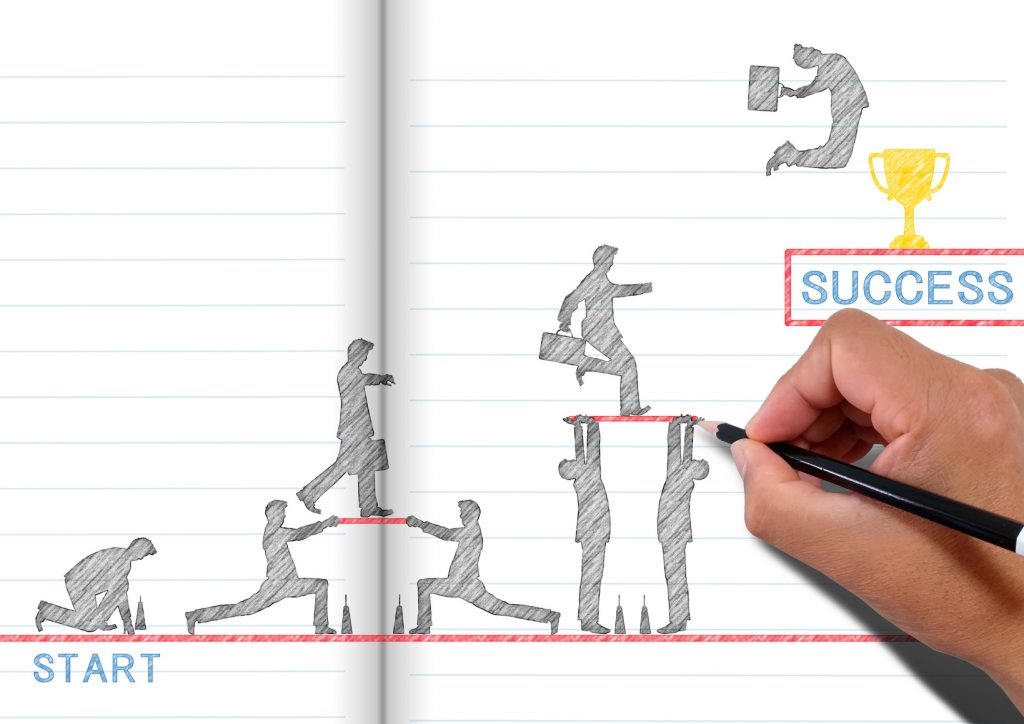
さて、この企業様は新人育成を3年計画で考えていました。新人育成には会社全体を巻き込まなければならず、そのためにはとてもじゃないが1年では間に合わない、と感じていたのでしょう。
とはいっても、何か特別なことをしたわけではありません。基本的には先ほど紹介した方法をもとに新人を育成する、ということを3年やっただけです。でも、実際に3年もたつと会社全体に「育成ムード」とでもいうようなものが醸成されてきました。それまでは育成や研修というと人事だけの仕事だったのですが、部署を問わず新人を育てよう、という空気になっていたのです。
それもそのはず、育成担当者を毎年違う人がこなしていけば、「育成担当経験者」が社内にどんどん増えていきます。育成担当経験者は育成のやりがいや楽しさを身をもって知っているので、今年の新人育成の後押しをします。3年もこの制度を続けていけば、こういったことが社内のいたるところで行われるようになり、やがては「会社全体で育てよう」という雰囲気になっていくわけです。
実はこの企業様、もともとは新人育成に積極的ではありませんでした。どちらかというと昔気質で、「技術は先輩の背中を見て盗む」という風土があったのです。でも時代の変化とともに、そうも言ってられなくなりました。会社のやり方についていくことができず、辞めていく新人が多発したのです。
でもそんな会社も育成担当者制度を導入し、一人一人に当事者意識を持たせることで、離職率を下げることに成功しました。
「新人が上手く育たなくて困っている」。こういう悩みを抱えている人事担当者はとても多いはず。まずは「育成ムードの醸成」を目標に、長い目で施策を考えてみてください。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊
成果主義、職務主義、年俸制、人事部廃止… 90年代から変わらぬ「人事」の構造、変わらぬ平均給与額が、日本を世界トップクラスの「社員が会社を信頼しない国」へと導いたのです。
なぜ変革が進まないのか、その背後に潜む「考え方」の欠如とは何でしょうか?

中学時代に習ったこと、覚えてますか?
多くの人にとっては、すべての勉強の基礎になっている大事な「当たり前」のことですが、思い出せと言われても思い出せる方は少ないでしょう。
この「この一冊ですべてわかる 人事制度の基本」には、人事の当たり前が詰まっています。

ー「なぜ、あの人が?」
なぜ多くの企業で「評価基準」が曖昧になっているのでしょうか。
どうすれば給与が上がるのでしょうか。
11,000人超の人事担当者から絶大な支持を得るコンサルタントが、今まで9割の会社が明かさなかった「絶対的な指標」を初公開!

テレワーク時代には「ジョブ型」に留まらず、「超ジョブ型人事」が不可欠。
その一番の理由は、テレワークをはじめとするこれからの働き方には「監視しない事が重要であるから」です。

人事の“必須科目”を押さえる
プロの人事力
次のステージに向けて成長するためのキホン
人事担当者に必要な知識・学び方、仕事に対する心構え、業務との向き合い方、さらには人事マネージャー、人事部長へとキャリアアップするために必要な能力・スキルを一挙公開

日本の人口の年齢別分布の現状と予想されている推移を考えると、
年功序列型の給与体系を維持するのは難しいと言えます。
年功序列型給与体系を脱却する糸口となるのが、「給与が下がる仕組み」です。
どのような基準で下がるのかを明確にする必要があります。

管理職って評価することはあっても評価されることはないと思っていませんか?
実は管理職であっても、評価基準やコンピテンシーは存在します。
会社が管理職に求めているコンピテンシーを理解して、
もう一歩先のステージへ挑戦しましょう。

求めるものがはっきりしていなければ、何をしても「ブレる人事」になります。
ブレない人事を実現するに、会社が求めるものを人事ポリシーで示しましょう。

採用活動というと面接を思い浮かべる方が多いと思いますが、
実は面接で得られる情報はそんなに多くないことが分かってきました。
これからは、客観的な評価ができる「適性検査」が採用活動の主役です。

人事には、人員計画・配置・採用・給与・厚生・育成・評価といった分野と、それぞれに戦略、企画、運用、オペレーションという機能があり、非常に幅広い分野の領域に関わる職種です。人事担当者は、どのように学習し、キャリアを構築していったらいいのでしょうか。本記事では、新任担当者から主力メンバーになるまでのキャリア構築の方法を「人事の学校」主宰・西尾太が解説します。今回のテーマは「人事学習のよくある勘違い」です。

「これはルールだから」と融通のきかない人事担当者は嫌われるもと。
とはいえ、人によってルールを変えていてはルールとして機能しません。
柔軟に対応することが大切ですが、
ではどのようにバランスをとればよいのでしょうか?

テレワークであっても成果を出すために、社員の働き方を監視する「監視ツール」を導入する企業が増えています。しかし、監視ツールを導入するよりも重要なのは、「適度なルール」と社員との「大人の関係」。
今回は、テレワークにおける人事管理の大事なことについてお話します。

脱・年功序列の実現で最後に必要になってくるのは、人事担当者の「想い」です。社会や顧客への想い、株主への想い、取引先への想い、そして共に働く人への想いがなければ、様々な抵抗に屈して改革は頓挫します。制度を変えて運用に成功している企業とそうではない企業の違いは、その原動力となる人事担当者の想いの強さにあります。総合人事コンサルティングのフォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP )の著者・西尾太が、人事担当者に必要な3つのマインドセットについて解説します。